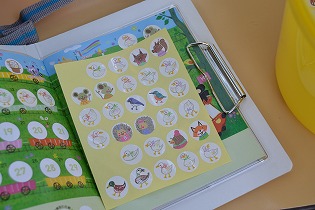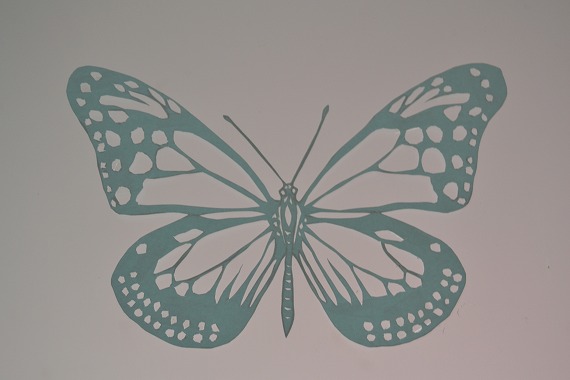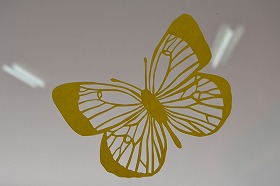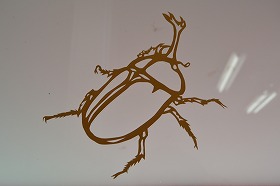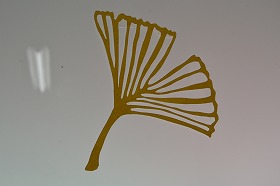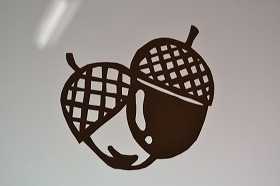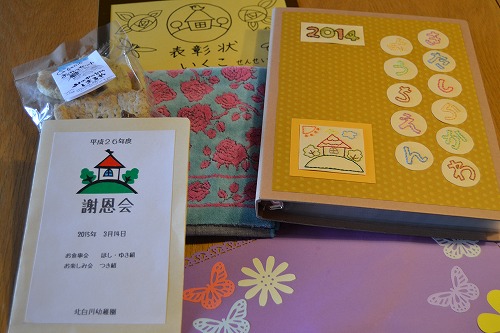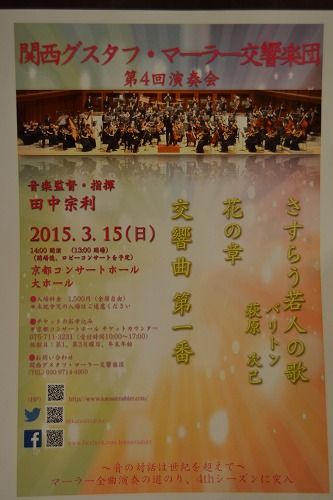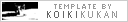2015.06.03
6月3日(水) / オークランド・ひみつの庭の“ママの日”だより(6/2記録)・園内通信

*************************
< バラ オークランド >
ニュージーランドにて作出
*************************
花瓶に入れておよそ一週間ほどになる、こちらは切り花“オークランド”。
咲き始めは清楚なイメージのバラでしたが、日を追って咲き進むにつれて淡いアプリコットオレンジの大輪に変わりました。先週末の午後、テラスに出してみました。
澄み切った青空に飛び交う鳥を眺めながら、久しぶりに家族でお茶の時間を楽しむことができたひと時。
花びらをみていると癒され、ほっとしてきます。
陶磁器には目がない方ですが、写真にちらりと写っているティーポットは1750年に創設されたイギリスCoalport(コールポート)社のもの。イギリス ウェッジウッド社の前身となるブランドで、現在は製造されていません。現在のウェッジウッド製品の中では、カントリーウエアのシリーズ(キャベツデザイン)がこちらのデザインを真似ているように思います。
傍らに、バードコールがあります。鳥のさえずりを真似るように空に向かって鳴らしていると、空高くから野鳥が反応してきます。ヒヨドリのような声?を出しながら野鳥と数回交信していると感じた時、驚くほど大きな鳴き声で反応する鳥がいました。何の鳥かは不明ですが、明らかに縄張りを主張する甲高い声にびっくりしました。
子ども達がひみつの森へ出かけた時にもバードコールを使用することがありますが、園庭でゆっくりと試してみても楽しめるかも知れません。
----------
ひみつの庭の“ママの日”だより(6/2記録)


昨日はママの日でした。10時半前にはすでに数名のお母さま方がお出で下さっていました。5月19日(火)ママの日に、築山の芝生に追加で種を蒔いてから約二週間。一カ月ほどで芝生が発芽するようですが、顔を近づけて見てみると大変小さな芽が出てきているような気がします。気がする、くらいで本当はまだまだなのですが、あと一息!といつも応援しているところです。さて、熊手、ほうきを用具置き場から運んでこられ、ウッドデッキ周辺をお掃除されるYママ、Iママです。


Tママも来て下さり準備されます。ビオトープについて何かとご教示くださるビオママことSママ。ベビーカーにOちゃんを乗せておられます。ちょうどお母さまが見える方向にベビーカーを置き、ビオママは防水スーツ着用で水の中へ。本格的! たくさん発生している藻を取り除いたり、排水溝まわりに手を入れて下さいます。
昨年5月1日には先生達とビオトープの生き物を容器に全てすくい上げ、水を全部抜いた後、再度水を溜めてから魚類を中に戻すという大がかりな作業を行いました。今年は空き時間を使ってりょうま先生が藻をこまめに取り除いて下さったり、少しずつ水を流して循環するように気を配っていたお陰か随分水は澄んでいます。昨年に比べると水は綺麗ですよ、と仰るTママ。皆の力が合わさり、多種類の生き物が変わらずビオトープで元気に生息しています。過日、私の目でざっと見えたところ、タナゴが25~30匹ほど、また琵琶湖固有種のゲンゴロウブナが10匹ほど。そしてクロメダカ多数。ビオママいわく、ゲンゴロウブナはただ今がちょうど産卵期とのこと。そう言えば、中にはお腹が膨れたように見えるものもいました。あと、ヌマエビが成長しているため、時折子ども達と手ですくって観察できますし、ヨシノボリ、小型のドジョウなどもどこかに元気でいるはずです。アメンボ、カエルは子ども達はすぐに見つけます。すでにシオカラトンボやオニヤンマなどが水まわりを回遊しながら産卵しているため、ヤゴもいます。ビオママいわく、ヤゴが水草の茎を噛むために水草が千切れて浮いてしまっているそうです。地上のお庭に手入れが必要なように、水の中もお手入れが必ず要りますが、なかなか十分なことができないままですので、折に触れてのアドバイスを有難く思います。


年長児Rちゃん達。お母さん頑張ってー!って言ってるのかな。ウッドデッキ下の里桜の植え込みエリアに下り、草抜き中のママ達。自由あそび中、縄跳びをしながらお母さんの近くまでやってきたRちゃん。お母さん有難う!


こちらはひみつの庭のフロントに植栽のミルテ。本当にまだまだ幼木で枝も細くて繊細です。木の下の方の葉が黄色くなり落ちてきているのに気付いたのが数日前。これは大変。土が固くなって水が十分に浸透しなくなったのかしら?と心配になっていたところ、どうやら栄養不足らしいことが判明しました。葉の黄化は、土壌のマグネシウムの不足が原因らしいとのことで、早速追肥をしてみることにしました。


新たな土に肥料を混ぜ込みます。大きなてみでも作業がし辛いので、私がよく使う手ですが一輪車の上で土の作業をします。子ども達も少しずつ手伝っています。時間がゆるやかに流れていきます。庭の作業は一人では遅々として進みませんが、人数が増えると二倍三倍に加速するように思います。


「ほら、みてごらん」とビオママ。ガラス瓶の中にいるのはタナゴの稚魚だそうです。見たところメダカの稚魚と判別できないほど似ていますが、中にスジが入っているので違うそうです。ビオトープのタナゴも三年目になりますが、産卵をしながら(水中の二枚貝の協力を得て)元気に生息しているのを嬉しく思います。泳ぐ親タナゴの背中にはオレンジ色の点が美しく見えます。


「ほんとだー」と子ども達。 桜の木の株元周辺に生えた実生や草などはどうしましょう?と相談中。


ここはヤブランが元気に生えています。近くの草はできるだけ抜いていきましょう。 新しい土はとても気持ちいいね。手の感触はどうかな?


ミルテの足元の土をシャベルでほぐしていく作業を子ども達が大勢で手伝ってくれました。肥料、酸素、水が十分浸透しますように。そして株元に水鉢をつくってあげます。


お庭の奥からホースリールを伸ばしてきて、優しいシャワーで水をあげましょう。そうね、株元にたっぷりとね。


ここにもお水をあげましょう。ふんわりとした黒い土に水が気持ちよく浸み込んでいきます。白くて小さな小さなつぼみをつけたミルテの木。どんどん大きくなって青々とした葉がまた生えてきますように。


お庭入口のサークルエリア。芝生の中に生えている不要な草を抜いて下さるYママ。何を見つけたのかな?この季節は、小さな生き物との出会いにも溢れています。

この日に集って下さったママ達。赤ちゃんをお祖母さまに預けて来られたママも。ご協力有難うございます。赤ちゃんのOちゃんもママと一緒にお庭まできてくれて有難う。可愛い笑顔でパチリ!
ダンボールで作れるというソファーは表面に皮を張って立派な家具に変身。また、すのこを使ったキッチン家具や下駄箱づくりなどなど、いろんな工夫を楽しんでおられるママ達。使わなくなれば解体してリユース、リサイクルできるメリットもあるとのこと。ママ達のアイデアは知恵や工夫に溢れていて感心します。
先日のお誕生会で私達が歌った二曲の歌「山のワルツ」「走れ超特急」などの話題にも。「歌はやめてやっぱり紙芝居にしようかな」と後ろ向きな発言になる太郎先生に、素早く二曲を選び、さっさと練習にこぎつけた私。と言っても前日のみの短い練習時間しかとれませんでしたが。「山のワルツ」は娘とよく歌った曲。また「走れ超特急」は私自身が幼稚園の年長児のときに元気に歌っていた曲でもあります。ピアノ伴奏も楽譜によって数種類ありますが、私の幼稚園児の時にはもっと激しく?賑やかな伴奏がついていました。左手をヘ音記号オクターブ和音で「ドシラソ、ドシラソ、~・・・」と、右手のメロディーとともに繰り返し続けます。なかなか豪勢な伴奏なのですがその楽譜が見つからず、現在あるポピュラーな楽譜で伴奏しました。5月お誕生会の歌のプレゼントとして、私達か歌うことで子ども達が非日常を楽しんでくれて何よりでした。
----------
さて、こちらはカプラ280ピース入りの箱。
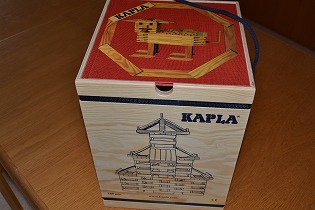
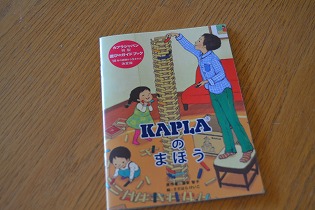
デザインブックが蓋になっている木箱入りで、先日新たに購入した年中児クラス用です。各クラスの自由あそびのコーナーの一つに常時カプラを置くことにしまして、年少児各クラス用は200ピース箱を購入。年長児はカプラ教室でも使用している大型1000ピース入りの箱カートを常時クラスに設置することにしました。
また、年少児クラスあそびコーナー用に、部品を組み合わせて大工さんの仕事をイメージして遊べる木製おもちゃを調達し、今週より使っています。子ども達は早速楽しんでいるようです。


こちらは昨日の1シーン。従来の竹馬が古くなってきたため、新たに完成品を30本導入しました。こちらの竹馬も体育指導のエール株式会社さんより送っていただきます。ただし、園庭のおもちゃ倉庫が満杯でしたので、掃除と整理をみんなで行いました。竹馬をする以前の年少児、年中児が取り組める手段として、追加で新たに竹ぽっくりを準備しているところです。
同じく、昨日のある屋根の上での様子です。ここはお山の中なので大変な量の春落ち葉が屋根の上、トユの中に積もり雨水が流れにくくなりがちです。葉や枝がしっかりトユをふさいでしまっている場所も毎年あります。大きな袋入りの落ち葉を何袋取ったかわかりません、と笑って仰るSさん。


三日間に渡り、計10棟の屋根とトユのお掃除を業者さんにお願いし、ようやく完了したところです。昨日は電気屋さんにも来ていただき、ご相談することがありました。子ども達の声が聞こえない時間帯も、いつも子ども達のことを思い浮かべながら明日の準備に励んでいます。
----------
本日は、園内通信「お知らせ27」「お知らせ28」をお出ししました。
内容は、
「お知らせ27」
◇ 父親参観のご案内
「お知らせ28」
◇ 家庭教育相談について
◇ 夏スモックについて
◇ 幼稚園児総合補償制度について
◇ 園児の健康について
◇ 未就園児さん対象“お山のミニミニ幼稚園”について