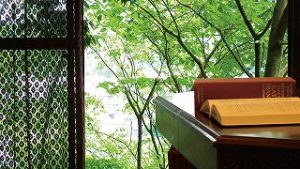
日本では外国語といえば英語を中心に勉強してきたわけですし、実用を考えればそれは当然のことですが、学問(大学は建前として学問を追究するところ)の基礎は英語ではなく(英語は手段)、ヨーロッパの古典語です(かなり強引ですが)。
ところが、日本ではすぐに成果のあがることに努力を傾注してきたため、お手本として仰いだ欧米の「今」を見てきたため、彼らが基本とした「ヨーロッパの古典」をほとんど無視して「日本の今」を築いてきました。それが世界の標準にどれだけ寄与できるのか?今問題になっているわけでしょうが、その鍵は世界の普遍的な「基本」が何かを探ることだろう(少なくとも何かを心得ていることだろう)と思っています。
もちろん全員がまなぶことはありえないとしても、ギリシア語、ラテン語・・・それなに?という現状はいかがなものか?と強く憤りを感じます。論より証拠、騙されたと思ってラテン語を勉強しましょう。本当は山の学校で、ギリシア語も教えたいのですが、需要と供給の関係で、今はラテン語止まりですが、将来はプラトンやアリストテレスも原文で読みたいものです。なお、山の学校では中学生もアリストテレス(翻訳)を読解し、自分の意見を発表しています。
私もキケローやウェルギリウスがどのようなことを信じ、何を訴えたかを一般の方が自習できるようなしかけを今後とも提案していきたいと思っています。ということで、私の個人的なサイトも少し化粧直しをしました。
>>「山下太郎のラテン語入門」
いまでも、ヨーロッパで大学の文系学部に進むには、ラテン語の入学試験が科されるところがありますね。厳密に言えば、バカロレアでラテン語の試験があるということですが。
はじめまして。ラテン語の勉強を何度も始めようと思っては挫折している Saturnian と申します。
ひとつラテン語で質問があるのですが、どこに記していいのかわからないので、ここに書いてしまいます。場違いであればお許しください。
英語の Grec<u>o</u>-Roman wrestling とか Ind<u>o</u>-European languages とか Russ<u>o</u>-Japanese war とか、あるいは、Archae<u>o</u>logy とか Bi<u>o</u>logy とか Soci<u>o</u>logy とかの接頭辞の語尾としての下線部の o は(下線が表示されなかったらごめんなさい。Greco、Indo、Russo などの o です)、ラテン語の格変化に由来していると思うのですが、正確なところはどうなのでしょうか?
もしお時間に余裕があるようでしたら、よろしくお願いします。
唐突な質問にもかかわらず、早々にご返事いただきありがとうございます。
詳細なご回答をいただいても理解できるかなあというのが正直なところだったので、これを機会に何度目かのラテン語入門をしながら、答えを気長に探したいと思います。
その後の変化を加筆しておきます。現在山の学校ではギリシア語も教えています。ラテン語の入門は、日本の教科書を使ったコースもあれば、海外の教科書を使った「帰納的」な習得コースもあります。古文の講読クラスに加え、この9月からは漢文コースもスタートします。