小学校で通知簿を廃止する動きがあります。
あわせて、子どもたちを見守る先生のまなざしが、幼稚園の先生のようであればと願います。
本園では毎月担任がひとり一人の園生活をふりかえり、コメントを各ご家庭にお届けしています。
年度末には「努力賞」を担任が一人ひとりに手渡します。
「こういうこと(課題)に対して、こういう点で努力できたでしょう(賞)」というひとり一人異なる文章を読み上げ、メダルと一緒に手渡します。
手渡すとき、クラスのお友達全員から自然と拍手が沸き起こります。
大人もそうですが、個々の努力に対してどういう形で先生がそれを「評価」するか、これは教育の大きなテーマです。
「山の学校」(幼稚園放課後の私塾)では、通知簿の類は一切ありません。
一般の塾、特に大手の予備校になると模擬試験の結果に基づいた合格判定なるものが常識化しています。
これも一つの「評価」です。
私は自分の学校時代の経験をふまえ、学校の成績も、模試の成績も、鵜呑みにしないことが一番大事だと信じて今に至ります。
合格判定程あいまいなものはないです。
20代から今に至るまで、予備校や大学で生徒たちと接する経験を重ねる中、年々模試の成績をうのみにする生徒だらけになっていることに驚きを禁じ得ません。
私は保護者にもよく、「試験の結果は話半分に受け止めてください」とお伝えしています。
学校の勉強といい加減に付き合えばよい、というのと逆のメッセージですが、なかなか伝わりづらい部分です。
本当に大事なことは、学びに向き合う真摯な気持ちです。それは数値化できません。
学力測定を数値化してはいけないというのではありません。それを他者との比較に用いてはならないということです。といっても、すでに時遅しですから、私は常々「話半分でよい」という態度をお勧めしています。
ではどうすべきか?といえば、自分の中に自分を叱咤激励する「理想に向かう」自分を育てることです。
私は山の学校の英語クラスを担当していますが、一人ひとりが自分を叱咤激励するように導いています。
配布するプリントは同じものが二つないように工夫して作成しています。
生徒たちは「隣の生徒」と競い合うのではなく、常に「過去の自分」を乗り越えるように努力しています。
昔、予備校で大学受験生の英語の指導をしていたとき、教材が難しく、私も調べないと解けない問題が散見されました。
そのような問題を、さも自分は簡単に解けるような顔をして生徒たちに教えることは自分の心が許さず、「私も調べて解いた。この手の問題は本番でできなくてよい」と述べ、一方、大学受験の問題でも中学で習うレベルの問題(想像以上にたくさんあります)に着目させ、そこで失点しないことが重要であると指導しました。
その後、大学でも英語の授業を担当しましたが、簡単な中学レベルの英単語を正確に書けなかったり、基礎的な文法事項があやふやなまま大学に合格したというケースが多数見受けられました。
ですから、偏差値がどうか、とか、学校の通知簿がよいとか、悪いとかとは別の尺度として、「自分は学校で学んでいる内容を年下の弟や妹に自信をもって教えられるだろうか?」という観点で自分を振り返る事が最重要な「試験」(自己チェック)だと思う次第です。
多くの場合、場当たり的に試験範囲の内容を覚えては忘れ…の繰り返しに終始しています。
自分で自分を厳しく見つめ、自分の向上を自分で喜び、自信に変え、日々努力を続ければ、おのずと道は開かれます。
その努力を怠り、場当たり的なやっつけ仕事のような勉強を繰り返し、試験の結果だけに一喜一憂すると、日々の学びが暗く不安でいっぱいになります。
揮発性の知識の集積と、大地に根の張った基礎の上に立つ知識の違いは大きいです。
また機会があれば教育講演会で具体的なことをお話しできたらと思います。

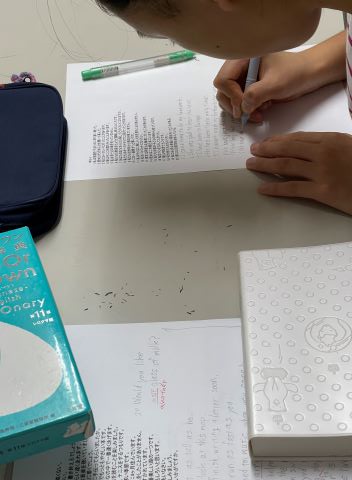
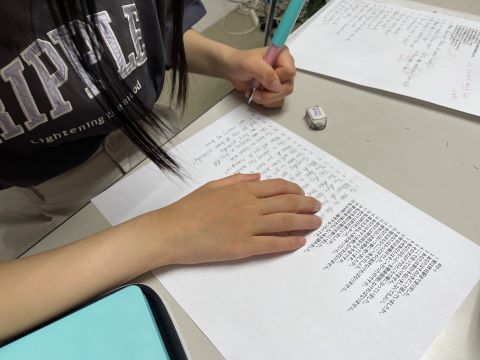
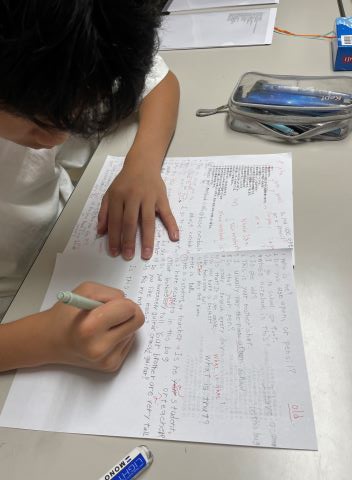






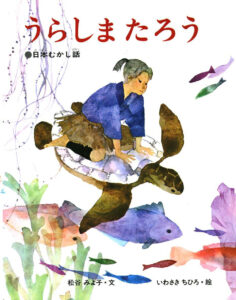
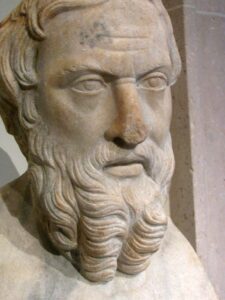
コメント