今日の資料は次のリンク先にあります。
講演会後ちょうだいしたご質問のQ&Aも含め、いくつか補足いたします。
Q. 『論語』を学びなおしたい。よい本はないか?
A. 『論語』にかぎらず、最初の一冊はできるだけわかりやすいものが望ましいです。司馬遼太郎は、「小学生向けに書かれた解説書・図鑑の類は本当によくできています。自分はいつもその手の解説書から未知のジャンルの学びを始めている」という趣旨のことを『独学の勧め』の中で語っています。あるいは岩波ジュニア新書もおすすめです。質問の趣旨とは異なりますが、『ギリシア人ローマ人の言葉──愛・希望・運命』(中務哲郎・大西英文著、岩波ジュニア新書)は西洋古典作品の文献案内を兼ねていますので、ぜひ一度お手に取ってみてください。世界が広がること請け合いです。今小学生のための論語、という言葉で検索すると、(日本語で遊ぼう)の斉藤孝先生の『小学生のための論語』という本が見つかりました。サンプルを見たところ、とてもわかりやすくてよい本だと思いました。蛇足ながら、「山の学校」では『論語』を注釈を用いて丁寧に読み解くクラスがあります。おすすめです。
Q. 子ども(年中児)から「死後の世界はどうなるか?」などの質問を受ける。自分自身哲学を学びなおしたいと思う。
A. 素晴らしいです。親子で哲学の本を一緒に読むのも一案です。『モモ』や『ソフィーの世界──哲学者からの不思議な手紙』であれば、読み聞かせや(家庭版)読書会のテキストとしてお勧めできます。再び蛇足ながら、「山の学校」では、哲学(=本当に大切なことは何かを根っこから考える時間)を楽しむクラスがいくつもあります。大人向けは先生との相性の問題もあるので、いくつか体験受講していただき、お好きなクラスを選んでいただくのがよいでしょう。ご遠慮なくお申し付けください。
Q. 子どもの日々の勉強を見ているが、どうしてもストレスを感じてしまう。
A. 大なり小なり子どもの学びを見守るさい、親はストレスを感じます。理想はストレスでなく喜びを感じることですが、一足飛びにそうならなくても、今まで曲がりなりにも継続してきた事実は尊いです。赤ちゃんの「はいはい」の話をしましたが、赤子の変化を見守るのは本能的に、必要以上のことを求めることは控え、手放しでその一挙手一投足を全肯定しやすいです。親として「(親としては)ここまで出来てほしい」という気持ちを少し緩和し、今日もこうしてわが子と一緒に勉強の時間を過ごせるだけで幸せだ、という原点の気持ちを忘れなければ、今後長続きします。運動会でいえば、親子レースで、親が子どもよりも前に先行して手を引っ張るのではなく、一緒に歩調を合わせて走ること、順位は度外視すること、がポイントです。今日お話しした、「(子どもの話があちこち飛躍するので)読み聞かせができない」というのも大いに「あり」とすれば、子どももリラックスして「お母さんとの勉強タイム」を楽しめます。お互いの時間を「楽しむ」のがベストですが、どうしても欲が出るのが親心です。もし親としてその気持ちが抑えられない場合、妙案があります。子どもでなく、親自身があえて脱線します。それは世間話ではなく、学びの掘り下げです。漢字であれば、子どもが学ぶ範囲の漢字について、先に徹底的に調べておきます。その知識を(ひけらかすのではなく)ほどよいタイミングで、これは実はこういう意味がある、等、掘り下げた話をしてあげます(子どもが興味を持つ程度に)。テストに出ることだけをやる、ではなく、むしろ、テストに出ない話を親自身が広く、浅く、ときには深く、子どもの学びの進度に合わせて、ご自分が自分の学びを深めるチャンスととらえて、あれこれ調べる癖をつけていけば、子どもとの「勉強タイム」の話題作りにもなり、お子さんは興味深く学ぶことを楽しめます。お子さんの性格など、この手の話は万事ケースバイケースなので、一概に何がベストとは言えませんが、親自身が「おもしろい!」と思う気持ちをベースにあれこれ試行錯誤するのがよいと思います。ときには学校の科目を離れ、ご自身の趣味や特技に立脚した話題をお子さんに伝授する時間に切り替えてもよいと思います。







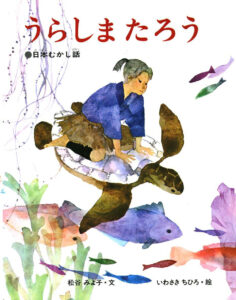
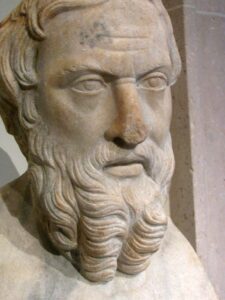
コメント