金曜日にお話ししたことのさわりを少しご紹介します。
その場で申し上げたこととして、ご家庭で「読み聞かせ」に加え、「読み合わせ」の会を開いてみてはどうかというお話をしました。
学校教育に対する不満の一つが、起承転結のついた作品(文学に限りません)の読解がおろそかになっていることです。
お父さんも1冊、お母さんも1冊、お子さんも1冊、同じ本を用意し、一人ずつ順番に音読し、交代していくやり方をご紹介しました。
読み聞かせの場合、本は1冊ですみますが、これは一人一人が読書サークルの参加者として対等の位置関係にあります。
本の選定は親が決めればよいと申しました。私はこれを家庭教師の先生と中学時代毎週行いました。
先生は理学部の院生でしたので、コンラート・ローレンツの「ソロモンの指輪」など自然科学の本が中心でした。
親の興味、子どもの年齢、様々な条件が異なるため、これがお勧めというのはあまり意味がなく、それをご家庭で決めることに意味があると思います。
とはいえ強いて候補をあげれば、定番はミヒャエル・エンデの『モモ』でしょうか。漱石の『ぼっちゃん』や『三四郎』も面白いです。
山の学校の「ことば」のクラスでは、今、コナン・ドイルの小説を丁寧に音読し、要約をしています。
赤毛のアンシリーズを読むクラスもあります。
御家庭の「読み合わせの会」の場合、音読のみで十分です。
読み合わせをする中で、子どもからごく自然に「これ、どういうこと?」という問いが生じます。
その問いを起点にして、さまざまな会話の展開が生まれ、生きた学びにつながります。
蛇足ながら、このプランのポイントは、ゆるく長く続けることにあります(週一ペースがよさそうです)。
継続するためには、必然的に大人が大人目線を捨て、童心に戻らざるを得ません。
子どもと同じ本を「ともに読む仲間」になることに最大の意味があります。
「教える」とか「成長を促す」といった大人の意識を捨てない限り、続きません。
大人が子どもと一緒に本を読む経験を分かち合い、どれだけ楽しめるかがカギです。
それを会得できた親子に対し、私から申し上げる言葉は何一つありません。
末広がりに幸せが舞い込むことでしょう。








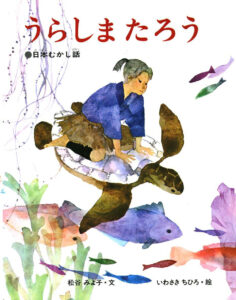
コメント