昨日の資料に次の一文を載せました。
国語力は、家庭と学校で養われる。国語力にとっての二つの大きな畑といってよく、あとは読書と交友がある。国語力を養う基本は、いかなる場合でも、「文章語にして語れ」ということである。水、といえば水をもってきてもらえるような言語環境(つまり単語のやり取りだけで意志が通じあう環境)では、国語力は育たない。ふつう、生活用語は四、五百語だといわれる。その気になれば、生涯、四、五百語で、それも単語のやりとりだけですごすことができる。ただ、そういう場合、その人の精神生活は、遠い狩猟・採集の時代とすこしもかわらないのである。言語によって感動することもなく、言語によって英知を触発されることもなく、言語によって人間以上の超越世界を感じることもなく、言語によって知的高揚を感ずることもなく、言語によって愛を感ずることもない。まして言語によって古今東西の古人と語らうこともない。ながいセンテンスをきっちり言えるようにならなければ、大人になって、ひとの話もきけず、何をいっているかもわからず、そのために生涯のつまずきをすることも多い」(司馬遼太郎、「何よりも国語」)
語彙が大切ということは、英語にかぎりません。文脈をたよりに「やばい」一語で様々な事柄を表わすことがご時世です、一つ一つの日本語の言葉と大切に丁寧につきあっていきたいものです。
ところで、司馬さんの文章は今からずいぶん昔に書かれたものです。私が危惧するのは、上の文の冒頭にある「学校で養われる」の部分です。これが実に心もとない時代になったと私は考え、昨日のお話をしました(学校の先生の責任ではなく文科省の責任です)。
問題は想像以上に深刻です。個人の感想を言えば、日本の教育がおかしくなり始めたきっかけは、私が高2のときに導入された「共通一次試験」です。その延長上に人文学軽視の風潮ができあがって今があります。
それはともかく、子どもたちにとってどうすればよいか?のカギは、消去法的に考えれば、おのずと「家庭教育」でカバーするという以外に見当たりません。そんなわけで、昨日は具体的な方法をいくつかご紹介しました。
会終了後、すでに私の提案を実践されているご家庭の例を複数の方々からじかにお聞きし、大変心強く思うとともに、子どもに代わって感謝の気持ちをお伝えしました。
AI時代に突入した今だからこそ、家庭での本の読み聞かせ・読み合い・(漢字の書き取り・親による文章の添削も)などの実践が有意義です。
学校も、一般の塾も、そうした取り組みはカバーしていませんが、山の学校では子どもから大人まで、そのような取り組みの実践が基本になります(広い意味で言えば英語・ドイツ語・フランス語・ロシア語・ラテン語・ギリシャ語・漢文などの「講読」クラスもじつは日本語の力を磨く時間になっています)。
よろしければ、お気軽にご見学・体験受講してみてください。







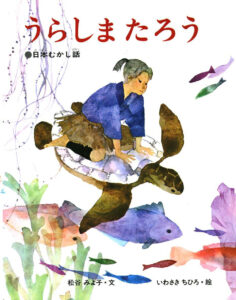
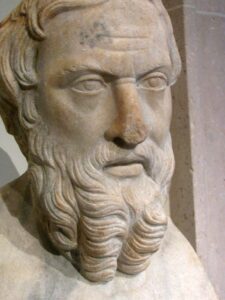
コメント