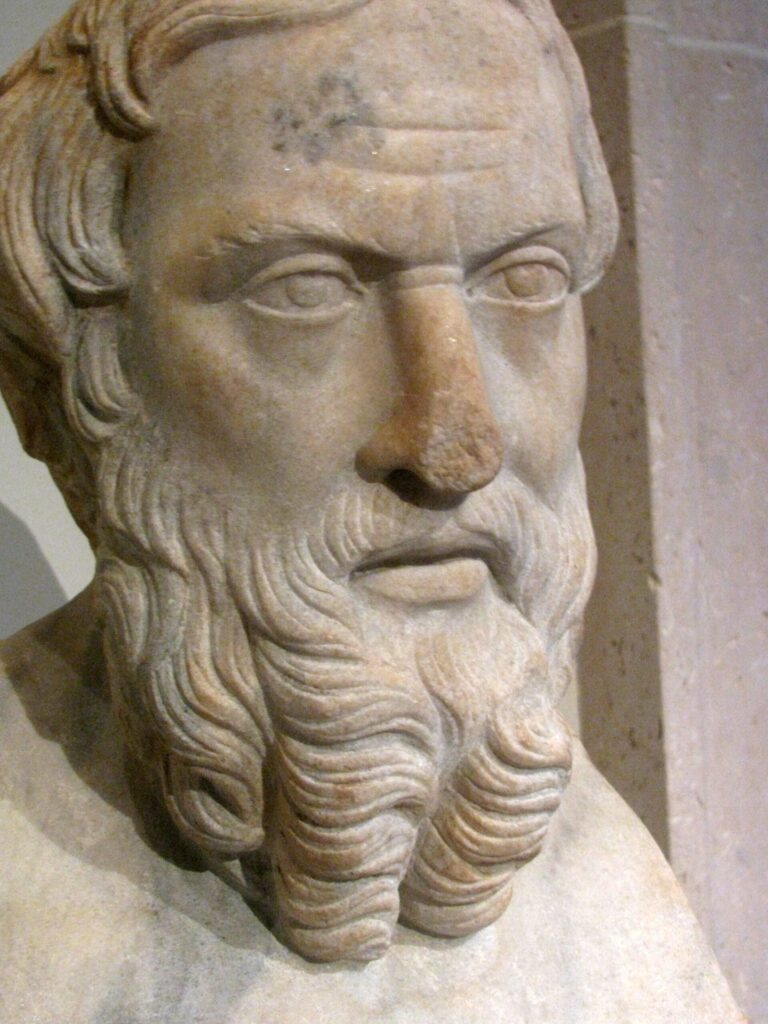教育– category –
-

2025-12-31 自然の中で遊ぶこと
養老孟子氏が「1日10分自然のものを見よ」と答えておられます。 「どうすれば頭が良くなるのでしょうか」という問いに対してです。 なぜ自然のものを見るといいのか? 養老氏によると、人は本来、目や耳から入る生の情報(感覚所与)を、脳が「意味」に変... -

2025-12-30 子どもらしく生きる
佐々木正美先生の言葉を紹介します。 「算数が苦手な子どもも、かけっこが不得手な子どもも、みんなで一緒に遊べるということは、そこに嫉妬のような感情はなくて、むしろ「○○ちゃんは走るのがい速いなぁ」と子ども同士みんなが尊重しあっているのです。子... -

2025-12-24 「浦島太郎」の絵本通信
以前「浦島太郎」の絵本を紹介しました。 >>おやまの絵本通信 そこに書きました通り、絵本にとって「絵」は大切です。 昔話を題材とした絵本は多いのですが、私はいわさきちひろさんの絵が好きです。 昔話を今に伝える言葉は絵と並んで大切です。 大人とし... -

2025-12-23 「知らぬが仏」考
今年はAI元年のようです。 未来を精緻に予想できるかのようです。 私はその点について懐疑的です。 科学が発達した現時点でも、死後の魂がどうなるのか、本当のところは誰にもわかりません。 自分の運命がどのような結末を迎えるのか、だれにもわかりませ... -

2025-12-18 『絵本と共に語らいを』──親子で紡ぐ幸福の原体験
以前「絵本通信」に寄せたエッセイです。 『絵本と共に語らいを』――親子で紡ぐ幸福の原体験 『万葉集』に「銀も金も玉も何せむに勝れる宝子に及かめやも」(山上憶良)という歌があります。どれだけ社会が変化し、多忙を極めても、親が子にそそぐ眼差しの... -

2025-12-02 子どもの「外遊び」の効果について:ナショナル・ジオグラフィックより
ナショナル・ジオグラフィックの記事をご紹介します。 >>子どもの「外遊び」は驚くほど脳にいい、一生ものの能力に影響 こういう研究成果を待つまでもなく、昔から子どもの遊びの価値は誰もが認める当たり前のことでした。 今は公園で遊ぶ子も、路地裏で遊... -

2025-12-01 情けは人のためならず考
「情けは人のためならず」ということわざがあります。 しばしば、「人に親切にしても相手のためにならない」という意味に誤解されがちですが、本来は逆で、「人に親切にすることは、巡り巡って自分に返ってくる」という教えです。 もちろん「自分への利益...