パソコンのファイルを整理していたら、次のタイトルの原稿が見つかりました。
本にも新聞にもブログにもどこにも使った形跡がないのが不思議なのですが、せっかくなのでご紹介します。
集中と一期一会
自園で俳句の時間を設けています。私が言葉を発し、子どもたちが声をそろえて復唱する、いわゆる素読形式です。俳句の取り組みのよい点の一つは、集中して聞く姿勢を持ち続けなければ何もわからない、という点にあります。
この日紹介した俳句は、「昼見れば 首筋赤き 蛍かな 芭蕉」というもので、私はこの俳句を通して、子どもたちに伝えたい言葉がありました。それは、「集中」の二文字です。蛍は普通夜に見ます。夜に見る蛍を思い出してみると、首のあたりが何色かはわかりません。でも、芭蕉は蛍をお昼間に見つけたのです。よく見ると、首のあたりが赤い、ということに気づきました。このことを俳句にしたわけですが、このようにじっと虫を見つめる経験は子どもたちにとって日常の世界です。
「このように息を潜めてじっと一つのものを見つめることをなんと言うでしょう?」と尋ねると、みなシーンとする中、一人の女の子が「しゅうちゅう」と答えたのには驚かされました。私は子どもたちに、自分たちが「しゅうちゅう」していると思う場面を思い出してもらいました。虫を探しているとき、「しゅうちゅうしている」。鉄棒で力を込めてふんばっているときも、「しゅうちゅうしている」。今日も、「しゅうちゅうして」黙想ができました。
こうして「できている」ときの経験を思い出してもらった後、集中しないといけないのに「できていない」場面を想起してもらいました。私が例に挙げたのは、お片付けの場面です。(遊び時間終了の)合図が聞こえているのに「まだいいや」と思ってぐずぐずしていないか、どうか。そう説明したあと、「これからお片付けの合図が聞こえたら・・・」と言うと、「しゅうちゅうする」と全員が声を合わせて答えました。
年長児ともなると、大人の言葉への憧憬が強まります。「ありがとう」という言葉は親しみのある大和古葉ですが、ときには例を挙げながら、「それを『感謝』と言います」と言うと、子どもたちの心には強く印象づけられるようです。
さて、卒園が近づいた別の日のことです。次の俳句を園児から手渡されました。
「ようちえん もうすぐおわかれ かなしいな」
さっそくその日の俳句の時間に紹介しました。子どもたちから「卒園式の夢を見た」という声も聞かれました。卒園が近づく頃、いろいろと子どもたちなりに悲喜こもごも交錯する時期ですが、上の俳句を紹介した後、私は子どもたちに次のことを言いました。
「何事にも始まりがあれば終わりがあります。楽しかったことが終わるときは残念だとか悲しいと思います。でも、まだ幼稚園は終わっていません。面白いテレビを見ているとき、最後まで目を離さず見ます。幼稚園もここからが面白いので目が離せません。今から一週間だとか、あと何日だと数えます。でも、みながやっている黙想は今日は3分です。全員で目を閉じて180心で数えるとその時間が「長い」と思います。幼稚園で過ごす時間は5時間です。どれだけ長いことでしょう。全部目を閉じて数を数えたら、「早く目を開けたい」と思うくらい長い時間です。「すてきだ!」と感じるのも、「よし、できた!」と思うのも一瞬です。一瞬とはまばたきする時間です。一瞬、一瞬でたくさんのことができます。たくさんのことを感じることができます。たくさんの出会いがあります。その一瞬が来週の卒園式まで数えきれないほどいっぱいつまっています。どんなすてきなことがあるのか、どんな楽しいことがあるのか、先生もわくわくします。「もう終わり」ではなく、「これからが始まり」だということです。このように考えて、すべての「出会い」をありがたいと思い、二度と来ない一瞬、一瞬を大切に思うことを、昔の言葉で、「一期一会」といいます。今から一週間、そして小学校に上がっても、一瞬、一瞬を大事に過ごしてください。」
これは以前保護者会でお話したことを子ども向けに言い直したものです。難しい内容ですが、実際にはもう少し噛砕き、最後に「いちごいちえ」と全員で声を合わせました。子どもたちは静かに聞いてくれたので、「何か」を感じてくれたと思います。








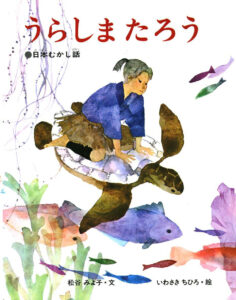
コメント