人間は便利を追求するようでいて、不便を楽しむ生き物のようです。
もし便利だけを追求するのであれば、誰も山登りはしないでしょう。
なぜ山に登るのかと問われた登山家が「そこに山があるから」と答えた逸話が有名ですが、補足すると、「山登りの楽しさを知っているから」ということだと思います。
山に登り頂上に着いた爽快感を知っている人は、日常生活で車を利用しても、山登りの不便を味わうことは厭いません。
人間は、便利だけに囲まれて暮らすとフラストレーションがたまるようです。
一般に「趣味」と呼ばれる世界は、どこまで不便を重ねても平気です。
大人はお金をかけて「不便」を楽しみます。
子どもも同様です。
大人以上に「不便」から遠ざけるように、世の中はよかれと思って様々な配慮をします。
しかし、子どもも一人の人間であると考えるなら、とことん不便の世界を楽しみたいと願っているのではないでしょうか。
子どもはなぞなぞやしりとり、クイズ、俳句が好きです。
わざわざ日常の言葉と異なる「めんどうな」言葉の世界を楽しみたいと思っています。
子どもとしりとりをした人はお分かりの通り、先に飽きるのはたいてい大人の方です。
同様に、子どもは車や自転車より、本当は「歩く」ことを楽しみたいと思っているかもしれません。
現代社会において、歩くことは「不便」の象徴のように思われます。
本園は75年の間、毎日1キロの道を手をつないで歩き、石段を登って小高い山の上の幼稚園に着きます。
家の前までバスが迎えに来てくれるご時世ですが、本園は戦後間もないころから令和の今に至るまで、このやり方は変わりません。
子どものころから、あえて「不便」を「楽しむ」経験をつんでほしいと願うからです。
そこに人生を謳歌する本質が宿ると信じるからです。
幼いころから「不便」を厭わない心を養い、「不便」を通して「楽しさ」や「喜び」を経験しておくことは、将来必ず自分を支える何かにつながると信じています。







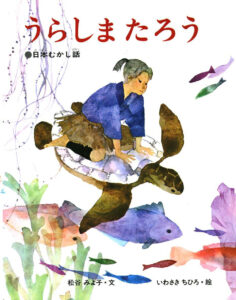
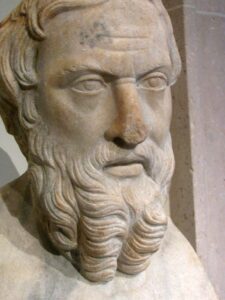
コメント