大人と違い、子どもはよく泣き、よく笑います。
子どもはなぜ涙を流すのでしょうか。
仕事柄子どもの涙は日常茶飯事で、その都度心の声を理解しようと努めます。
そのような経験を整理して、以前次のような一文を拙著にまとめました。
泣く子は育つ
四月は涙の季節です。入園したばかりの子どもたちは朝の通園時に保護者とスムーズに別れにくい一時期があります。そうしたときは、子どもを抱っこして、いったん親から引き離します。泣きじゃくる子どもは私に悪態をつくこともあれば、「ママがいいー!」を連呼しながら号泣することもあります。
抱っこして道を歩きながら、私は子どもの耳元で「先生は○○ちゃんと幼稚園にいきたいな」「幼稚園に着いたら、お庭のチューリップを見に行こうか」などなど、さまざまな励ましの言葉を繰り返します。子どもはそれでも「ようちえんにいきたくない!」と言い続けます。
しかし、子どもは泣くだけ泣いたら、必ず自分で歩こうとします。今まで、グループの集合場所から園までずっと抱っこし続けたケースはゼロです。泣くだけ泣いて、言いたいことを言い続けた子は、意外にケロッとします。こんなやりとりは、年少児一学期の風物詩といえるものです。時折思い出したように、秋以降も、あるいは年中になってからも、私の「抱っこ」が必要なケースもありますが、それは一時的なものです。
私たちは、年少の最初にどれだけ泣こうと、ちょうど大雨に見舞われても「やまない雨はない」と達観できるように、それが永遠に続かないことを知っています。だから、心では余裕をもって子どもを抱きかかえ、なだめながら送迎の道を行き来できるのです。心では「がんばれ、がんばれ」と応援をしながら。
周りの子どもたちも、その子を心の中で応援しています。そして、ひとしきり泣いたその子が歩道に降ろされ、自分で歩けるようになったとき、「よかったね」と自分の弟妹のことのように安堵していることが顔に書いてあります。
先日、ある年長児が言いました。「ぼくもちいさいぐみのとき、○○ちゃんとおなじやった」と。そのとおり。私は今もその子の泣きじゃくる姿を昨日のことのように思い出します。私が「ちいさいぐみのとき、だれと手をつないでもらってたかな?」と尋ねますと、「△△ちゃんにつないでもらってた」と、こちらが想像する以上に当時のことをよく覚えています。「そやしな、ぼく、いま○○ちゃんとてをつないであげるねん」とその年長児は力強く言いました。
子どもたちが自分の意思で「一人で幼稚園に通う」と腹を決める日は必ず訪れます。これは、おそらく植物や他の動物にはない、人間固有の「決断」です。私は、今まで何百回も見てきました。涙を流しながら初めて親に手を振った子どもの姿を。
思えば、人間は「オギャー」と泣きながら人生のデビューを飾るもの。節目、節目で泣くのが自然かもしれません。ふりかえると、歴代の「大泣き」のシーンが次々とよみがえります。「あんなに泣いてばかりいたあの子が、野球部のエースで大活躍!へえー!?」この手のニュースはまさに幼稚園の先生冥利につきる大切な宝物です。
涙は年少児だけのものではありません。年中児・年長児が大泣きすることもあります。それは勝負に負けて流す「悔し涙」です。我が園では秋の運動会で徒競走やリレーを行います。本番に限らず練習の段階でも悔し涙を流す子がいます。
競技をするにあたって、子どもたちには、勝ち負けの大事さととともに、一生懸命がんばること、転んでも諦めずに走ること、バトンを落としてもしっかり走ることの大事さをお話ししています。そうして真剣に取り組んだからこそ見せる涙です。実際には泣かなかった子どもたちも、間近で友達が涙を流す姿を見て、自分の中に「真剣に勝負に挑む気持ち」を目覚めさせているようです。同じ運動会の場でも、大人の競技に出た保護者が負けて涙を見せることはありません。それに対し、子どもたちにとって、運動会というイベントは、当日も練習の日々も、すべてが真剣勝負なのです。だからこそ大事な節目で「泣く」のでしょう。運動会が無事に終われば、こどもたちは精一杯力を出した爽快感を味わい、次の飛躍に向けての自信を得ます。
年長児になると、自分の非を悟って流す涙もでてきます。ある年の冬、劇のけいこの途中に舞台の袖でふざけ始める子がいました。注意をしても耳に入らず、なおかつ、周りの数名の子もそれにつられてしまいました。そこで、私はその日の練習を最後まで終えた後、クラス全員の前でお話をしました。
「本番を前にして緊張するのはわかります。しかし、ふざけたり、笑ってごまかすことで真剣勝負を逃げてはいけません。自分の番が終わったら劇が終わるのではありません。舞台の上の人も、舞台の袖の人も、みんなで力を合わせてこそ、いい劇ができるのです。だから、がんばりましょう」と。静かな口調で諭していると、思い当たる数名の子が涙を浮かべて聞いていました。これも成長の節目で見せる涙と言えるかもしれません。
涙のクライマックスといえば、卒園式です。ある年の卒園式の翌日、次のようなメッセージを保護者から受け取りました。
「卒園式、謝恩会を後ろで見守る最中も、お歌を歌いながら、食べながら、スライドを見ながら、両手で頬をぬぐう我が子に幾度となくハンカチを差し出そうかと思いましたが、本人は一度も振り向かず、ずっと前を見据えている様子でしたので、私もその姿をみつめました。こんなに静かに泣く姿は初めてでした。家路についてしばらくして娘が、『かなしいとなくでしょ。うれくても涙でてくるでしょ。それから、かなしいけどうれしいときも涙がでるんだね』とつぶやきました。そして今日、時折、強い春風の吹く中を散歩していたら、
『かぜさんと おててつないで ひとっとび』
と、うれしそうに言いました。それがなんだか晴れ晴れしい笑顔で、どんなときでもきっと子どもは一生懸命前を向いているんだなと強く思えました。」最後の「かぜさんと・・・」の言葉は、「よしっ」というふっきれた思いと少し背伸びした気持ちが、幼稚園で学んだ俳句の形に凝縮されています。卒園式という節目を超え、次の未来に向かって元気に「ひとっとび」していく。そんな子どもらしい潔さが目に浮かびます。こうして年少から年長までの三年間をふりかえると、幼稚園生活は「涙に始まり涙に終わる」という言い方ができそうです。子どもたちが節目で流す涙には、それぞれに大事な意味が宿っているのです。
最後の「かぜさんと・・・」の女の子は今も「山の学校」に通ってくれています。幼稚園時代の清らかな心が今もそのまま輝いています。








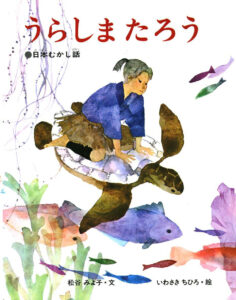
コメント