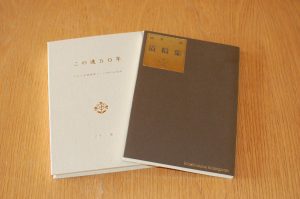私の子どもの頃は、 およそ茫洋混沌(ぼうようこんとん)としていて、この子はいったい何を考えているんだろう、どこを見ているんだろうなどと思うと、両親も恐らく頼りない思いに駆られていたに相違ない。
「いや、子どものころは、妙にこせついたのよりは、これでいいんだ。」と父親あたり、あるいは納得していたのかも知れない。その私が、人並みに物書きを目指したい、などと大それた野望を抱きはじめたのは、中学一年生のときである。宿題で、作文を書かされたことがあった。題は自由である。規定は一〇枚ということだった。
ちょうどその頃は戦時中のことで、私は北白川の山の上の家から大分離れた、一乗寺のうちのいも畑の夜番のために、二坪足らずのいも小屋で寝起きをしていた。その夜宿題のテーマが決まらず、寝つかれぬまま、私は夜半小屋の表へ出た。通りを隔てて、すぐ前に迫っている雑木林の木の間隠れに、月が神秘なまでに冴(さ)え返っていた。その青白い光を浴びながら、そばを流れる清水の清冽な響きを耳にする内に、ふと、同じような場面の三年前の回想に耽り始めていた。
その三年前の回想をテーマに、その夜からの私は、まるで物の怪(け)に憑(つ)かれたように毎晩おそくまで書きつづけ、規定をはるかに越えた百数十枚の、随筆とも小説ともつかぬものを纏めて職員室の戸を叩いた。
期限に遅れること三日、半ば不安なような、半ば期待に胸を膨らませながら立っている私に、「何だい、こりゃ」母の心尽しで、茶色いボール紙で表紙までこしらえた分厚い原稿の束を、机の上に無造作に置くと、首藤先生は眼鏡越しにジロリと私を見られた。「はい、宿題です」教練仕込みの、活発な語調で答えた。「規定無視だな。 ともかく読んではおこう」「はっ、お願いします」と四五度に頭を下げて立ち去ろうとすると、「しかし、違反の点はすでに減点だぞ。覚悟して居給え」と睨んで、「スッス」とあだ名された首藤先生は、最後は悪戯(いたずら)っぽく、「スッスッスッ」と、独特の含み笑いをも洩らされた。
十日程たって、作文の時間。今日あたり、この間の宿題の結果が分かるんじゃないかと思うと、胸が異様にときめいた。生まれて初めての作品らしいものに対する反応が表れる。ベルがなって、首藤先生が胸いっぱいに原稿の束を抱えて入ってこられた。その中には見覚えのあるボール紙の茶色も混じっていた。短い批評とともに、宿題が一人一人の手に返された。先生が時折用いられる諧謔に、部屋中がどっと沸き返った。
全部が配り終えられたとき、「どうしたんや。お前、出してへんのか?」隣の山川が、私の空の机の上を見ていった。「あれや」と、首藤先生の教壇に残された、たった一つの私の作品を目で促(うなが)してから首をひねった。「今日は一つ、参考作品を読みましょう。 題はこういうんだ」首藤先生はそういって、くるりと後ろ向きになると、白墨をもって黒板へ字を書こうとされた。そのとき、部屋中が思わず嬉しさにどよめいた。無造作な先生の、大いなる失策である。ワイシャツの裾が、上着の下から無遠慮に覗いている。しばらくは教室内、笑いが揺り返し、押し戻した。中には机を叩いている奴もいる。
あとで私は、首藤先生に職員室へ呼ばれた。「少々、センチメンタルな所もあるが、抒情的で素直な文だ。これからもどしどし書くといい。「年輪」の編集長にもいっておくから、出来たのは持っていきなさい。ただし、規定は固く守ること。それともう一つ、ここにも書いておいたが、この作品は山が二つに分かれている。どちらかを切って整理するか、両者をうまくまとめて統一するか、あくまでも素材に食いついて、生かしきることだ」。懇篤(こんとく)な批評と激励までいただいて、薄暗い職員室を私は明るい気持ちで出た。
家へ戻ると、父が、陽のよく当たる縁側で正座を組んで、のんびりと日向ぼっこをしていた。父は、わたしの報告を聞くと、「それはよかった。さっそく仏さんへ供えてこい。源(げん)伯父さんも喜ぶぞ」私は源伯父の霊の合わせ祀ってある、先祖の位牌の前に作品を供え、手を合わせた。首藤先生に指摘された、二つの山の一つをなすものが、富士見高原療養所に病む、在りし日の源伯父の姿をテーマにしたものだった。作文のテーマのきっかけとなった、一乗寺の澄んだ月光とせせらぎの瀬音が、父と療養所を訪ねた日の信州の夜を思い起こさせたのだった。
この伯父は、父の畏敬(いけい)するすぐ上の兄で、生涯を独身で通し、神戸にある会社の要職にあって、多忙な中の余暇に親しむ文学だけを、終生の伴侶とした。後年胸を病んで、伯父が薄幸な生涯を療養所に閉じる、少し前のことである。たまたま、父が十年の労作を処女出版することになった。それを知った伯父は、わが事のように喜んだ。
すでに死を予期していたのであろうか、活字にならない前の原稿を、ぜひ送って欲しいとしきりにせがんだ。不自由な床で、その原稿の悉(ことごと)くに目を通しては、時折朱筆を遠慮がちにそっと入れ、超世間的な父の文体に、常識人としての受け取り方はこんなものじゃなかろうか、と気を使ったりした。伯父の亡くなるのと前後してその本は出版され、伯父の霊前を空しく飾った。
いままた、亡き伯父をテーマにした私の作文が先生に認められて、伯父の霊前に供えられている。「お前が、物を書くような仕事にでも携わったりしたら、特別お前を可愛がってくれた伯父さんのことだから、どんなに喜ぶだろうな」呟くともなく呟いた父の一と言が、妙に私の心にしみついた。そしてそれまで格別に気負った考えもないままに、少年時代をのんびりと過ごしてきた私の心に、初めて夢といえるような、野心の灯がともされるのを自覚した。それからの私は、機会あるごとに筆に手を染めては、つぎつぎに「年輪」に投稿した。そのつど、伯父の霊前には、真新しい活字のインクの香りが漂った。
中学三年の春、戦局は悪化して私達は学徒動員で飛行機の部品工場に配属され、旋盤のダイヤルを握った。ようやく機械の操作も板についてきた八月半ばに終戦を迎え、私達の京都一中は、学制改革によって洛北高校となり、昨日までの中学生が一夜にして、高校生として遇されるようになった。戦前の高校生に対する畏敬と憧憬の念を抱いていた私達には、急に馬子(まご)が礼服を着せられたようで気恥ずかしかった。何もかもが、突如として起こった変動であり、教育を与える側も直ちには教育理念や方法の切り替えに戸惑ったため、勢い、ブランクの時間が多かった。
しかし、私にはむしろこのことは幸いした。校内の図書館に入り浸って、東西の作家に触れる機会を多く持つことが出来た。続いて秋には、教員、生徒を含む画期的な大異動が、京都府下一斉に行われ、私達は中学以来の古巣洛北高校をあとに、元府立一女の鴨沂(おうき)高校へ配置換えをさせられた。ここへ移ってからも、相変わらずブランクの時間は多かった。有難いことに、ここの図書館は規模も大きく、蔵書の数も多かった。ときには、代返を頼んで図書館につかる術も覚えた。
新しく編成されたクラスに、坂田というのがいた。彼は歌舞伎を好んで、ほとんど月代わりにこまめに劇場へ足を運んでいた。以前から歌舞伎の好きだった私は、彼と意気投合し、時には乏しい小遣いの底をはたいて「二代目中村雁治郎襲名披露興行」を観劇しに、大阪千日前の歌舞伎座まで出掛けたこともあった。四階の立見席からは、新雁治郎も豆粒のようにしか見えなかったが、それでも少年二人には大変な感激であった。したがって、そのころは図書館へ行っても、歌舞伎鑑賞のための日本古典文学に意を注ぎ始めていた。近松、黙阿弥はいうに及ばず、五瓶、正三、南北、治助、近くは逍遙、綺堂のものなど、手当たり次第に読み漁った。舞台を見ながら、今から思えばおままごと染みてはいたが、手帳に批評の真似事を書き込んで、あとで互いにその批評を批評し合ったりもした。
一日、「板東蓑助を囲む会」を私達の高校の文化部で催したことがある。私もたどたどしい口吻(こうふん)で「演劇におけるリアル論」を顔赤らめながら一席述べたところ、蓑助丈から、「若い人の中に、このように熱心に歌舞伎を愛好し、研究してくれる人がいることは頼もしい。貴方のご意見に似たようなことを、岡鬼太郎さんや、岡本綺堂さんもいっておられますよ。今後も大いに芝居を見て研究して下さい。お宜しかったら資料も提供しましょう」と、少年に希望を持たせるための、過分のお褒めの言葉を頂戴した。それに勢いを得て、「近松と黙阿弥」を百枚ほどに纏め、蓑助丈を南座の楽屋にお訪ねしてご覧に入れたのも、この頃の懐かしい思い出だ。
文学にあこがれ、歌舞伎に傾倒していた私は、高校三年に、選ぶところなく京大文学部を志望した。頭脳構成の偏頗な私は、まったく不得意な理数科の幾つかの問題に手を焼き、その年の受験は敢えなく失敗に終わった。高校生とはいってもいわば成り上がりの、中身の貧弱な私達が、多年の浪人組に名を成さしめたとしても、当然の結末であったのかも知れない。「新制高校第一回生の面目にかけても、きたるべき入試には頑張ろう。」と友人達とたがいに手紙を出し合い、励まし合いながら、浪人一年目の生活は光の箭(や)のように過ぎ去っていった。
師走に入り、小雪が舞った。いよいよラストスパートをかけるべき時期に入った。そんなある日、「やってるか?」と、父が入ってきた。私は無言で微笑した。「うん。じゃあ、また後で話そう」出ていこうとする父に、「なにか?」「そうだな、少し息を入れるか」「はい」私は、アンダーラインで真っ赤になった、化学の参考書のページを閉じた。「実は、弱ってるんだ」「?」「お前に今こんなことを話すのは、気持ちを乱してよくないんだが」どんなときでも姿勢を崩したことのない父に、私もきちんと向かい合って正座した。「幼稚園をやることになりそうだ」「えっ?うちが!」「うん、俺が園長だ」と、苦笑しながら言った。私は唖然とした。「お前の今の驚き以上に、俺自身が、現在まだ呆然自失の態なんだ」「…」「実を言うと、一つには売り食いの種に尽きてしまったんだ」このことは私も薄々感じていた。そのためにもこれ以上、徒に浪々の身をかこつことは許されないと、受験勉強にも一段の真剣味が加わっていたのだ。「何かしなけりゃいけないと思っていた矢先、京都女子大の方から、先生の話があった」私には、父がこれを断ったであろう理由は容易に察せられる。
父は、三高、京大の学生時代から、極度の眼精疲労に悩み、眼を使わずに理解したり覚えたりするコツを会得して、幾多の試験を乗り切ってきた、とよく話していた。それまでに、二冊世に問うた著書も、終日氷枕で眼を冷し、辺りの静まる夜陰(やいん)に起き出ては、眼をこすりこすり絞り出すようにして書き上げた労作なのである。講義の原稿を書き、試験の答案を見る眼があれば、少しでも新たな著述の方に使いたいに違いない。「講演や、座談会といっても、暮らしを潤すほどには掛かって来んしな」
そこへ、勤め口やら、恰好(かっこう)な仕事を頼んでいた、父の親しい友人の一人で、地元の有力者の一人である西村氏が、話を持ち込んできた。「先生、ひとつ幼稚園やらはったら、どうです」「幼稚園?」「はあ」「私が?」「そうです」西村氏は、何やら自信ありげに静かに笑っていた。
この北白川のあたりは、平安朝の昔より、御所へも花を入れていた由緒(ゆいしょ)ある町で、格式の高い家も多い。それに、昭和十年頃から移り住んできた、京大を中心とするインテリの学者達も、今では相当な数に及んでいる。この両者の人達によって構成されている、いわば京都でも一・二を争う文化地帯だ。ところが七不思議とでもいおうか、この北白川には、一つとして独自の幼稚園がない。子ども達はみな疏水を越えて、他の区内のいくつかの幼稚園へ通っている。今までにも何度か「北白川に独自の幼稚園を」の話は持ち上がったが、結局適当な人と場所を得ず、物にならず終いに終わっている。
「先生の仕事探しに奔走してます内に、将軍地蔵の離れの集会所が空いたから、どやろ、あそこで、この際先生に幼稚園やって貰うたら、こんな声が急に盛り上がってきたんです」と西村氏は、勢い込んで言った。「冗談じゃない、私は、その任ではないよ」父は笑って、頭から取り合わなかった。「そんなことありません。 先生は教育に対しても、なみなみならぬ関心を」「持っていることと、実際にやれることとは、また、別問題だよ。作家と批評家との関係のようなものだ。それに幼稚園ともなれば、一応、経営の才もいるんだろう?」
西村氏は、得たりとばかり相好を崩して、「大したことはありませんよ。 たかが幼稚園ですが」「それがいかんのだ。たかが、という気持ちで子どもを預かるわけにはいかんよ。かりにやるとしたら、私は全身全霊をあげて打ち込みたい」西村氏は、少し慌てて眼をしば叩かせた。「おっしゃる通りです。だからこそ、先生にお願いしたいんです。それだけの教育的熱情と誠意を埋もらせることはありません」「それが駄目なんだ。私は一人で思索する仙人のような男で、青年相手ならまだしも、大勢の幼児達に接するなどは、難中の難事なんだよ。」「でも先生、やって見られないことには」「いや、たとい作り笑いをしても、幼児はついてこない。幼児教育には全く向かない男なんだ。私は自分をよく知っている」しかし、西村氏は諦めなかった。それからは、三日にあげず押しかけて来て、来るたびに地元の有力者の誰彼(だれかれ)を連れて来ては、共々熱心に頼んだ。
時には深夜に及ぶこともあった。だが、父の答えは変わらなかった。「渋られるから、よけい、お願いしたいのです」そういって強引な西村氏は、父の思惑をよそに、「あそこの建物の一部を園舎にあてて、そのためには持ち主のお寺へ交渉に行って借り受けましょう。庭には木が植わり過ぎていて運動場には不向きですから、少し間引いて石段の両側へ植え込みましょう。なあにそれぐらい、私が若い者を連れてきて、奉仕しますよ」などと、まるで気のない父の前に、あれこれと頭の中に描いた設計図を拡げて見せた。「君、私には全然やる気がないんだよ。先走りしてもら貰っちゃ困るよ」「何、構わんです」その内に、通園路の道普請(みちぶしん)の奉仕を申し出る人が現れたり、「あの土手に滑り台をかけたら、ほかでは見られないユニークな滑り台ができますよ。私が一つ腕を振るって上げましょう」と無償の協力を申し出る人も現れたり、父の思惑とは裏腹に、事態は次第にひとり歩きをし始めてきた。
そうこうしている内に、何より驚いたのは、「お宅で幼稚園をなさいますそうですが、規則書を一部頂けませんでしょうか」と、子ども連れの若いお母さんが、わざわざ山の上まで訪ねてきたことだ。「どちらでお聞きになりました?」「はあ、あちらこちらで」「ほう!」規則書にもなにも、躍起になって勧めにくる西村氏その他の人達の矛先を、いかにして躱(かわ)そうか、そのことに苦慮している最中だ。
だが、さすがの父も、この申し込み者第一号の出現には、いささか慌てざるを得なかった。幼稚園設立の噂は、すでに北白川一円に広がっているようだ。どんな形で流布されているかは知らないが、ぐずぐずしてはいられない。最終態度をはっきりと決めなければならない。(仮にだ。作るとした場合、園舎の借り受けは一応西村氏に任せるとしても、まず第一に設立の資金は?教育内容は?職員の陣容は?その俸給は?第一、こんな山の上まで子どもが果して来てくれるのか?また、今頃から園児の募集が可能なのか?園長として、自分は子ども達に何をすればよいのか?自分が子どものお相手になれるのか?)あれを思い、これを考えると、自信の持てる材料は何一つとしてない。
実はその頃、かつて父の書いた著書を読んで、父の元で勉強したいという人達が四人、地方から出てきて、父の借家に住んでいた。父は、この人達たちと一乗寺の畑で農耕をしたり、父の家に集まってきた四人の人達に朝の講義をしたりしながら晴耕雨読の生活を送っていたのだった。
ある朝の講義のあと、父は、西村さんを始めとする地元の人達の一連の動きについて、話をして見た。すると、中で一番年かさの宮下さんは急に顔を輝かせて、「先生、そりゃいい。おやりになったらいい。わたしもぜひ、お手伝いさせていただきます」宮下さんには、自分の気持ちを汲んで、当然引き止めてくれることを期待していたのに、少々裏切られた思いで、「何を言うんだ。私は極力断っているんだよ。私がこの仕事に向いていないことは、君がいちばん良く知ってるはず筈だろ。むしろ君が孤軍奮闘の私の代りに、止め男になって西村さんらを説得してくれることを期待して、この話を出したんだよ」
しかし宮下さんは、ひるまなかった。「先生には、最適の仕事だと思います。先生は、ただ教育理念の指導者として、頭に乗っかって頂くだけでいいんです。頭のお考えに基づいて、私も、妻の靖子も、実際指導面においては、惜しみなく協力させていただきます。わたしも教師の経験を持っていますから、何かのお役に立てると思います」「といっても、台所事情もあって、資格をもった正規の先生さえ雇えない状態では、お給金だってろくに払えないんだよ」「どうぞご心配なく。幼稚園の運営が回転するようになったら、いつでも頂きますから、それまでは喜んで奉仕させて下さい」宮下さんは更に語を継いだ。「わたしは、音楽の部門を受け持たせていただいて、靖子は、お遊戯の方のお手伝いをします。先生の教育哲学をもってすれば、きっと良い独自の幼稚園ができると思いますよ。こりゃいい。楽しみだなあ」宮下さんからは、逆に、さんざん発破をかけられる始末となってしまった。
この宮下さんは、元学校の先生をしていたが、今はピアノを教えている音楽家である。奥さんの靖子さんは、当時若手のバレリーナとして、将来を嘱望されていた人である。「だがねえ、私は人との交際は下手だし、それに第一、事務的能力はゼロなんだよ。役所への手続きなど、大変なんだろ?」と、まだ未練がましい父に、四人の中では一番若い湯本さんが、「そんなことなら、ご心配には及びません。府庁への認可申請手続きのお手伝いなら、私にさせて下さい」とこれまた父の逃げ道を遮ってしまうのだった。
正に八方塞がりもいい所だった。そうした、足元の協力体制がしだいに整い始めてきた頃、「じゃあ、私は、お絵描きやお細工を担当しましょう」と名乗りを上げたのは母である。父と結婚する前に上村松園女史に師事していたときの、昔取った杵柄(きねづか)をこの際生かそうとの申し出である。こうして、父の心配の一つ、基本的陣容と給料の面はなんとか整いつつあった。
昭和二四年の暮れも押し詰まった頃のある日、西村氏が顔を紅潮させて入ってきた。「先生!朗報です。島津源蔵氏が、山下さんがやるのなら、名誉園長を引き受けても良いと言っておられます」同じ町内に住む誼(よし)みとはいえ、世界的な発明王と謳われた島津氏(島津製作所の創設者)が、まだ誕生さえしていない幼稚園へ、山下個人を信頼して、名を貸そうと言っておられる。また、そこまで動かしている西村氏のなみなみならぬ熱意。四人の学徒の全面的な協力、勿体ないほど有難い、多くの人達の心尽くしではないか。今はもはや、思い惑うている時ではない。これほどまでに信頼してくれる人達の期待には、誠意をもって報いなければならならない。人生を出直したつもりで、幼稚園のイロハから取っ組んでみよう。父の心は漸(ようや)くにして決まった。
やがて府庁の文教課へ、北白川幼稚園設立の認可申請書は提出せられた。昭和二五年二月一一日のことである。(当時、二月一一日は建国記念日ではなく、平日であった)認可申請書には、設置理由がつぎのように述べられていた。「京都市左京区北白川学区は、市内における有数の文化地域にして、幼稚園のごとき教育施設を最も必要とするにもかかわらず、未だ一ケ所もその設備を見ず。元よりそれがため、早くより要望の声上がり、現に区内児童公園内に某公共建築物を移転援用して、これが設置の運びに到りしも、複雑なる事情のためその成功を阻まれ、今は中断の形にあり。されば、学区内幼児は車馬の危険を冒して、遠く吉田、浄土寺、養正等、他地区の幼稚園に依拠する次第にして、ますます『北白川に幼稚園を』の願いに駆り立てつつあのが現状である。
ここにおいて、地元有志者は『北白川幼稚園設立後援会』なるものを創り、『北白川のための、北白川住民による、北白川の幼稚園を』創設することを目的として、禅法寺所有にかかる将軍地蔵付設の瓜生会館を借用なし、同会館下に住む山下英吉にこれが事業を委嘱せり。ここにおいて本人は、同人の独自の教育精神によって、自然と文化の融和の下に、幼児の心身の発育を助けるとともに、真の人間の根幹をつちか培わんとするものなり」
申請書提出のその夜、ここまで盛り育ててくれた人達によって、やがて生まれ出づる北白川幼稚園の前途を祝して、心ばかりの祝杯が酌み交わされた。西村氏のあっせん斡旋で、無事建物の借り受けもできた。設立資金は、最後の切り札として取っておきの土地の一部を手放して充てることにした。あまつさえ、熱心な数名の人達が率先して、設立後援会を組織し地元を駆けずり回って、浄財を集めてくれた。
これは、後にも先にも父が快く引き受けた、只一度の寄附金であった。案じていた立地条件も、園医になってくれることとなった河根先生が、「むしろ最高至上の条件に叶っています。緩慢な山の上り下りの運動は、保健上、なかんずく脚力の増進に役立って、心身ともに快適な子どもが育つでしょう。私も大いに人に勧めましょう」と、太鼓判を捺してくれた。幼稚園の指導スタッフも揃いつつある。こうして見ると、絶望視していた設立のための諸条件のいくつかは、いつの間にか一つ一つ片付いて、前途にもやや明るい見通しがついてきた。
父はその夜久しぶりに、打ち寛いだ気分にひたることができた。宴半ばにして西村氏が立って父の真向かいに正座した。「先生、今日の門出に当たり、一つ、粗品を呈上致したいと思いますが」西村氏は改まった言葉を、少しおどけた調子に包んでいった。「まだこれ以上、何か?」父は、恐縮とも当惑とも付かぬ面持ちで、火鉢の上に翳(かざ)していた手を、膝の上で揃えた。島津氏は、何ももっていない西村氏の手元を、不思議そうにチラと見た。和服姿の西村氏はやがて袂(たもと)から巻紙を取り出して、父の前に置いた。
「ご覧ください」父は訝(いぶか)しげに巻紙を手にとって、するすると拡げて見た。紙面にはぼくせき墨跡も鮮やかに、荒いタッチで人名が十人分ぐらい書きなぐられている。いったい何の人名やら見当もつかない。「これは?」「今度お世話になる園児達です。一一名やっとかき集めました」瞬間、一座の空気が緊張した。「そうですか!」父の口許から深い吐息が洩れた。「短時日に、よくそれだけ集められましたね」大原氏も、感嘆の声を遠慮なく吐いた。「ちょっとした、四十七士の連判状(れんぱんじょう)だな」と島津氏が、座の空気をほぐすように言った。父は、熱っぽい眼を島津氏に向けた。「正しく、討ち入りの覚悟です」「すると差し向き、私が一番老骨だから、堀部弥兵衛金丸ってところかね」低く呟くように言った島津氏の冗談に、人々は大きくどっと笑った。その夜は時の経つのも忘れて、父は気持ち良く談笑した。
さて、その人達の去った後、一週間の心労のせいか目ばかり冴えた床の中で、又してもわ沸き起こる焦燥が、良心をチクチクと責めた。(だめだ。やっぱり俺には無理だ)(このご期に及んで、何を言うんだ)(肝心の条件が欠けている。俺が幼児教育に向いていないということだ。これは致命的な問題だ)(慣れだよ。何だって初めからうまくいくもんか)(違う。泳ぐ術を知らぬ者が、溺れる子を助けに飛び込めるか?慣れでは遅い。子ども達を初めから慣れの犠牲に出来るか)(馬鹿をいえ、賽(さい)は投げられたんだ)(いや、今なら取り消せる。まだ間に合う)翌日、府庁の文教課の戸口の前を、行きつ戻りつしていた父は、やがて、思い切ってドアを開けた。女子事務員が、気の毒そうにいった。
「今井主事なら、たった今、お出になったところです」「たった今って?」「そうですね。 物の二分くらいも前だったでしょうか」「二分? 二分なら玄関前までは長い廊下だ。途中で逢(あ)う筈じゃないですか」「それが、今井主事はいつも、中庭を斜めに抜けて行かれますので」「ああ!」 廊下と中庭。同じ府庁内を僅か二分の差で、二人は別々の方向へ足を向けていたのだ。今井主事の不在のため、幸か不幸か、認可願いの取り下げはできなかった。二分、タッタ二分。父は、府庁の玄関前の砂利道を、その言葉を何度も何度も反芻(はんすう)しながら、ゆっくりと歩いた。(俺は既に、運命の支配下にある!)
抗すべくもない運命の厳しさを、まざまざと感じた。さしもに思い惑うていた父も、ここに至ってはっきりと、幼稚園設立へ向け心を決したのである。細長い建物の廊下のガラス窓に、松の枝が写っている。裸の桜のこずえ梢が滲(にじ)んで見える。その前に、太い物干し竿が宙に一本浮いている。物干し竿には、湿りを含んだおしめが十数枚、戦後の住宅難にあえ喘ぐ庶民のように、寸分のすきま隙間もなくひしめき合っている。温かい日差しにおしめから立ちのぼる湯気が、白い炎のようにまぶ眩しく揺れている。滴りがポトリと落ちた。
「ここでやるんですか?」文教課の江田係長は、そのおしめを呆れたように見上げて言った。「はあ」「確かに、ここに入ってる引揚げの人達、出てくれるんでしょうね」「あと五日で、出ることになっています」振り絞るような声だ。「ほかの条件は一応揃っていますし問題はないとしても、この建物の今の状態を見る限り、私達も、いい加減な許可は職責上できませんのでねえ」江田係長は今井主事を振り返って、何とも色よい返事をしかねる様子だった。
私達の住んでいる山の上に、将軍地蔵というお地蔵さんがある。ここには瓜生将軍といういくさの神様が祀(まつ)られているということで、戦時中は、出征兵士や応召兵士の幟(のぼり)が堂を狭しと埋め尽くされ、武運長久を祈る読経(どきょう)の声が終日聞こえていた。身内を戦地に送りだした家族もひっきりなしに訪れて、戦時中の山はたいへんな賑(にぎ)わいを呈していた。そんなところから、将軍山とも呼ばれていた。ところが国破れて訪れる人も絶え、将軍地蔵に隣接する講の人達の集会所である瓜生会館も空き家同然となり、現在では引揚者の仮の住まいとして提供されていたのである。
父は、一歩江田係長に進み寄った。顔と顔がぶっつかりそうになった。「係長さん、私が飽くまでも責任を持ちます。今この中に住んでいる引揚げの人達を、一時私の借家へ移してでも、決してご迷惑はお掛けしません」江田係長は、無言で父の顔を見た。沈黙は長く続いたように感じられた。やがて、今井主事と眼と眼で頷(うなづ)き合ってから、江田係長は静かに微笑を洩らした。「分かりました。取りあえず、役所へ帰って松本課長とも相談の上、近日中にお返事することにしましょう」
それからの幾日間か、父や、西村氏や、そのほか北白川幼稚園の誕生に期待をかけてくれている人達はすべて、文教課長の決断いかんを不安な表情で鳴りを潜めて待っていた。問題の建物に雑居していた三所帯の人達も、江田係長一行の視察後五日目に約束通り出てくれた。後片付けも終わり、認可を合図に一斉に内部改造が行われるよう、手筈はすっかり整えられていた。昭和二五年二月二八日、認可は遂に下りた。申請書を二月一一日に提出してから、様々の葛藤(かっとう)を経てやっと辿り着いた、もはや逃れようのない結論である。
「さっきも言った通り、大体この話の起こった動機というのが、うちの経済問題から出発しているんだ。従って、正式の保母が一人も雇えない。そこで、絵やお細工は、お母さんが受け持ってくれることになった。音楽は宮下君、お遊戯は靖子さん。それぞれその道での一流の人材だ。みな殆(ほとん)ど無償で参加してくれる。三人とも、幼児を相手にするのは初めてだが、きっと一風変わったいい成果を挙げてくれると期待しているんだ」父は一気にそこまでいうと、「そこでだ」と膝を乗り出した。「ここで一つ欠けているのは、子どもと泥んこになって、専門に遊んでくれる遊び相手だ。
俺は幼児教育の中での遊びという面を、非常に重視している。そこでどうだろう。お前は生来子どもが好きなようだから、無理を言うようだが二年間だけ手伝ってくれんか」「えっ、僕が。二年間?」「そうだ。済まぬが、基礎の固まるニ年間だけ、受験を延ばしてくれると有り難いんだがなあ」「でも第一、幼稚園で男の先生て、ないんでしょう?」「俺は大体が、既成の幼稚園の概念を払拭させるつもりでやるんだ。だから構わないと思う。一寸調べて見たんだが、幼稚園には今のところ、こうでなければならんという、固定した教育理念ってものがないんだ。新しく鍬(すき)をうちこむ余地が、非常に多く残されているようだ。将来お前がどういう道へ進むにしても、このニ年間の人生経験は、相当お前のためにもなるんじゃないか」
私の今の驚きは、父が幼稚園を始めると聞いたときの比ではなかった。容易に頭の混乱は納まりそうになかった。父は続けた。「大学へ入っても、アルバイトをしなきゃやって行けないような、うちの状況だ。だから、二年分のアルバイトを先にやって、家庭の経済が回転し始めてから、あと、ゆっくりと学業に専念するという考え方だな。虫のいい注文か知れんが、今うちとしても大事な岐路に立っているんで、一つよく考えてくれんか」
父は、急には回答の出そうもない私に微笑でうなずいてから立ち上がった。襖(ふすま)を開けて出ていこうとしたが、思い直してくるりと振り返ると、「俺もこう追い詰められちゃ仕方がない。やる以上、実践教育の面では恐らく無理だろうが、幼児教育の思想家として、西にフレーベル、東に山下あり、の気概でやるつもりだ。初めは手さぐりでも、その指先にピリピリと神経を通わせて、かならず何かを掴んで見せるよ。どうだ、俺と一緒に生きた勉強をやらんか」父は出ていった。
私は畳の上でゴロリと仰向けになった。天井の縞目(しまめ)がくるくると渦を巻いた。私は一層落ちつかない気持ちを静めるため、外へ出ようとして茶の間を通った。飯台の向こうに坐っていた父が、「尤(もっと)も、手伝うといっても、送り迎えと子どものお相手だけでいいと思うから、後は受験に備えて勉強に専心していいからね」父の向かい側に坐っていた母が、窺うように私の顔をじっと見つめていた。
私は外へ出た。春に近い太陽が真上にあった。時折り風が音を立てて、土手の上の笹原を渡っていく。私は石段を老人の足取りのように、一段一段ゆっくりと踏んでいた。この石段の上に将軍地蔵がある。かつての賑わいに反して今はほとんど訪なう人もなく、ひっそりとした石段を、あと二た月を経ずして、新生日本の次代を背負う幼い子ども達が、ふたたび毎日のように上がってくる。時の流れは、石段を踏む人達を変えてしまったのだ。私は段を上がりきって、幼稚園の園舎に予定されている瓜生会館の前に立った。すぐ隣の将軍地蔵の出窓がギシギシと開いて、足腰の不自由なお婆さんが、窓のへりから首だけ出してこちらを見た。
「一郎さんか?」「お婆さん、お身体の具合、どうですか?」私は出窓に歩み寄った。中気のこのお婆さんはほとんど奥で寝たきりで、季節を取り違えたように温かい今日の日溜まりで合わせる、かれこれ一年ぶりの顔である。「おおきに、相変わらずや。寒い日なんか痛うてな」お婆さんは、皺だらけの顔へ不自由そうに手をやって、鼻を啜(すす)った。
「一郎さん、今どこ行ってんのや?」「去年、高校を出ました」「ほんなら、大学か?」「いいえ、去年は失敗して、浪人です」「また、受けるんやろ?」「さあ、そうしたい思うてるんですけど、どうなりますか」「大丈夫やがな」お婆さんは、なにを勘違いしたのか、一人で目を細めた。「そやけど、あんたもよう大きうなったもんやな。今やから言うけど、あんた、ほんまは育たん思てたんやで」お婆さんは、顔と声とを震わせながら、私をまじまじと見つめて言った。
好いお婆さんなのだが、たまに顔を合わせると、いつもこの無遠慮な言葉を判で捺したように繰り返されるのには、実のところ少々辟易(へきえき)気味であった。「百草のおかげや。あんた、うちの百草で命助かったようなもんやで」これも決まり文句である。百草は、修験者だったお爺さんがまだ存命中、木曽の御嶽山へ寒行にいっては貰ってくる、竹の皮に包んだ黒い小判型のくすりである。それを分けて貰っては火にあぶ焙り、柔らかくして小さな丸い粒を沢山こしら拵えておくのである。一日に五粒ずつ決まってのませらのだが、片栗粉にまぶして縁の白っぽくなった黒い固まりは、見ただけでも唾の出てくる素敵滅法苦いものであった。毎日のまされ続けて慣れるにつれ、ほんの瞬間舌の上に乗せるだけでぐっと咽喉の奥へ押しやるコツを覚えた。後で貰う一粒の飴玉の必要がなくなっても、苦そうに渋面を作っては、笑顔で睨む母からまんまと飴玉を貰っていた。
何しろ、私の幼少の頃のひ弱さときたら、お話にならなかったそうだ。それでも、生まれた時は三六〇〇gもある、まるまると太った赤ん坊だったらしい。ふとしたことが原因でひどい肺炎に罹ってからは、腸をすっかり駄目にして、それからの私は成長を全く忘れてしまったかのように、百草のおかげも勿論あろうが、何よりも両親の献身的な介護を受けながら、辛うじて寿命を保っていたに過ぎない、という状態だった。アイスクリームについているウェファス、あんな赤ちゃんにでも消化の良いものも、固形物の故に、食べたあとは一週間下痢のし続け。数えの四つまでは近所の同じ年頃の子どもが、棒切れを振り回して走り回っているのに、頭ばかり大きく、手足は針金のように細く、立つことも叶(かな)わず家の中をゴロゴロと這いずり回っていたのである。
タッタ一人の男の子がこのような状態である。両親はどんな思いでいたであろう。その情けなさ、歯がゆさは察するに余りある。「初めて立ったのが、数えの四つの年の五月一二日だったんよ。それからは随分ましになったようね」と、母は今でもよく洩らしている。小学校へ入ってからも余り丈夫だったとはいえず、第一恐ろしく小柄で幼児用の服が四年生まで着られたというのだから、スーパー級のチビであった。病気もよくしたが、それが決まって長期の休み中のことで、学校の方はほとんど六年間を無欠席に近い状態で過ごしたのだから、不思議みたいなものである。私が現在のように、薬物はおろか、医者に手一つ握って貰わず、人並みの背丈と健康を保って活動出来るようになったのは、中学一年の頃からの急速な成長以後のことである。それまでの節制と、両親の言葉に尽くせない忍苦と愛情が、この年になって一度に実を結んだのかも知れない。そんなわけで、私ぐらい幼い頃から身体のことで両親に苦労を掛けた子どもは、そう滅多にはあるまい。
さいきん戯れに、友人と神社の境内の易者を冷やかして、そのとき開口一番、「あなたは小さい頃に一度死んだ身体だ。ある種の使命があなたを蘇らせたのだ」と、大時代な表現で言われて、慄然としたことがある。「きっと育つまいと思うてた」と会うたびに繰り返す、お婆さんの言葉とも正しく符節(ふせつ)を合わせている。私は、物ごころがついてから、いつの日か両親の一方ならぬ労に報いたいものと、その心は常に私の生活信条を支配していた。折りも折り、私の幼児期を苦労で押し通した両親が、今また、同じ幼児の問題で苦境に立たされている。著述家の常として、物臭(ものぐさ)な父が毎日マントを引っかけては、下駄の音も慌ただしくどこかへ出掛けて行く。茶の間では父と母が顔を寄せて暗澹(あんたん)たる面持ちである。「ひと度幼稚園を設立して、運営途上挫折するようなことにでもなったら。」とそれを思うのであろう。
私の手伝いがプラスになるかならぬか、それはわからない。しかしここで親子が心を合わせ創業に体当たりした挙げ句、それで挫折してもまだしも納得はいく。国家存亡のときには、私達中学生は学徒動員で旋盤のハンドルを握ることを強制された。私も、その時は当然のごとく参加したではないか。今は、わが家が危急に瀕(ひん)している。にも関わらず、家のこととなると父も言いづらそうに頼むし、私も咄嗟(とっさ)の判断さえ下せない。これは何故だろう?二年の受験延期が、それほど大問題なのか。長い人生の一瞬の足踏みに過ぎないではないか。私は、飛び込もう!父は府庁の玄関前で、運命を感じた。私は将軍地蔵の出窓の前で、中気のお婆さんから私の過去に触れられ、私の生き方に翻然と目覚めることが出来た。
「お婆さん、僕、やっぱり大学、今年は行かんことにしましたわ」何のことやら、呆気にとられたお婆さんを後ろに、私は一目散に石段を駆け降りた。爾来九年間、私は保父の座に着きっぱなしである。初めの内は大学生活を思い、文学を思い、歌舞伎研究を思い、二年のブランクへの未練が尾を引いた。それと共に、私を捉えたのは、(いくら一時の手伝いとはいえ、大の男が幼児のお守り役とは)気恥ずかしい、面はゆい思いであった。朝な夕な子どもたちの先頭に立っての送り迎えが楽しくはあるが、正直な話辛かった。バスの中で出会った子どもから、「いちろうせんせえ!」と、大声で呼びかけられると、嬉しさと同時に、周囲の人達のびっくりしたような視線を困惑気に、顔を火照らせた。当時京都市内でも、いや恐らく日本中探しても、男の幼稚園の先生は滅多(めった)に見られなかったからである。しかし、そうした気恥ずかしさに耐え、面はゆさに顔赤らめながらも、やるときは懸命であった。すると、世間の見る目が違ってきた。
「男の先生には、女の先生にない、また別のよさがあるやないの」そしてそれが、「幼稚園には、絶対に男の先生も必要やわ」いつの間にか、そう変わっていた。父が、幼稚園を始めて二年目の、二学期頃であったろうか、こういった。「見てると、お前は幼児教育のために生まれて来たような男だな。人それぞれに使命がある。うちの園において、お前は一瞬たりとも保父の座を空にするわけにはいかんようだ。どうだ、思い切ってこのまま続けてやって見んか」二年間の腰掛けのつもりでいた私の脳裏を、前の時にも増して大きな衝撃が走った。今度は単に一時の手伝いのことでなく、私の運命の路線を決定づける、一生涯に関わる問題だったからである。
「初志を貫いて自分の夢を生かすか、父の言う使命(ゆめ)に身を任せるか」私の心の動揺を見透かして、父が続けた。「教育学も心理学も、生きた実践をしながら書物を通して裏付けていったり、疑問を抱いたり、それを解明しょうとすることは、大学で観念的な学び方で終わる場合より、ずっと自分のものとして身につくんじゃないかな。もちろん、それだけの努力は大学へ行く以上しなければならないし、俺も少しは力になるつもりだ」
私はその時、次第に冷静さを取り戻していた。というのは、何よりも、私は小さい時から父を畏敬していたからである。これまでにも私が何かするたびに、父がそれをどう評価してくれるか、それは誰に言われるよりも私に取って大きな反省となったり、励みとなったりした。その父が一年半の私の保父振りを見て、その適性を認めてくれたのだ。これはわたしにとって大きな喜びであった。やがて熟考の末、私は父の意に従った。しかし、それからも毎年春を迎えるたびに、二つの夢はから絡み合った。が、それも次第に私の念頭から離れていった。父の言う使命(ゆめ)が身について来たからであろう。
父の見通していた私の使命に、そのとき素直に同調していけた事を、今となっては、しみじみ幸福に思っている。よく子どもたちは、「一郎先生は、一番こわいけど、好きや」といってくれるそうである。私はこれを聞くたびに新たな感動を覚える。「やさしいから、好きや」とは、よく言うところである。だが、「こわいけど、好きや」とは、男性幼児教育者として、かくありたいと願うからである。子どもたちはまた、私のことを、「いちろう先生」をもじって、誰がつけたか、「いちご先生」とあだ名している。私は初夏の強烈な陽射しに、青い葉陰から顔を覗かせた、しみ入るように真っ赤ないちごの純情が好きだ。青年の今の純情を持ちつづけて、白髪の翁(おきな)となる日もなお、「いちごせんせい!」と呼ばれつづけたいと、私は思う。
>>第3章