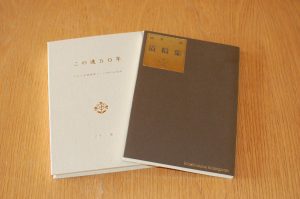疲労の大掃除
「今やから言うけどな。陰ではみんな、育たんやろ言うて噂してたんやで」
幼児期に大病を患ったおかげで、桁(けた)外れの発育不良の状態が続いたため、近所の人達からはそう見られていたわたしも、その後は次第に体調が整い、中学以降はいちおう人並みの線を維持してきたつもりである。
ただ、幼稚園の仕事に携わるようになってから二度、どちらも大よそ一ケ月間床についていたことがあった。
一度は、幼稚園創設二年目の五月、ある日突然耳が聞こえなくなった。ほとんど失聴状態である。痛みもある。
父が、「お前はお前なりに、昨年から幼稚園のことで相当神経を使ったのだろう。聞こえるようになるまで思い切って休め」
父の診断は当たっていた。医者にも行かないのに一と月ほど経ったある日、茶の間のラジオの音が微かに聞こえてきた。蘇る喜びを実感した。
しかし、一つ悔しいのは、この間にあった遠足に参加出来なかったことだ。五〇年間で、春・秋合わせて一〇〇回の遠足のうち、タッタ一回の不参加だった。
今も耳は健全とはいえず、年中、蝉時雨(せみしぐれ)が耳の中を覆っている。
もう一度は、幼稚園とは直接関わりのないことだが、次男が中学の時、次年度の育友会長に指名されたことがあった。その前年、副をやっていたので、こんど会長を受けるとなると、かなり困難な問題を抱え込むことになると予測していたので、脳血栓で倒れて臥せっている父の枕元で相談をした。父は黙って聞いていたが、口許を微かに動かした。判読すると、
「やれ」
と読めた。
お受けしたその年の秋、ある日突然足の関節がきり錐でも揉むように痛みだした。日増しに痛みは募り、鮫に食いちぎられる痛みとはこのことかと思われる激痛が、毎日つづいた。痛みは関節から関節へと渡り歩いている。寝返りも打てない。もちろん、送り迎えにも行けない。
これも予期していた通りの心労のなせる業かと、耳の時の例にならい医者には行かず、思い切って痛みの取れるまで静養することにした。
寝ている部屋のそばを、三才児が部屋へ駆け込む足音を、焦れったくも羨ましく聞いた。ほぼ一ケ月ほど経って、少しずつ痛みが引いてきた。何時までもこうしてはいられない。そこで初めて医者に来てもらったら、さっそく一本の注射を打たれた。ふだんから薬や注射に縁がないせいか、たまの注射が抜群に効いたものと見え、翌日は嘘のようにすっと立つことができ、二、三日すると完全に園に復帰することができた。
二度目の最後こそ注射の恩恵に預かったが、それ以外は、医者とは全く無縁で過ごしてきたと言っても良かった。
また、わたしは不思議に毎学期ごとに、学期が終わると二、三日高熱を出すか、腸をこわすかする。そんな場合、いつもじっと籠もって寝るか、絶食をして腸の負担を軽くすることにしている。
幼稚園は楽しい仕事だといっても、全く疲れを伴わないわけではない。学期間に溜まった精神的な埃(ほこり)を自然に大掃除しているというわけだ。
そんなことで、今まではできるだけ自然治癒を心掛けていたので、少なくともわたしの身体にメスの入った試しは一度もなかった。それが思いも掛けぬ手術のため、一ケ月の入院を余儀なくされる羽目に陥ったのである。
昭和五九年九月のことであった。
運命に身を任せる
わたしはその三年前から、京都府私立幼稚園連盟の四〇年記念誌の編集を任されていて、五九年の三月にようやく発行の運びとなった。
一方において、あるグループの幹事の要職を五八年七月から五九年六月までの一年間持たされた。もちろん幼稚園の方も例年通り勤めていた。だから五九年という年は、特別忙しさの重なった年でもあり、ストレスの溜まった年でもあった。
この年の正月すぎから、わたしは身体の変調に気付き始めていた。便に鮮血が混じっているのである。それも繁忙に取り紛れ、痛くない痔だろうぐらいに思うことにして、健康診断に行くこともしなかった。
六月になって双方の激務から開放され、ようやく私学共済の健康保険を使って、東福寺の近くにある第一日赤の半日人間ドックに入った。
数日後、結果が出た。担当医師はカルテを一通り見て、
「特に異常はありませんね」
ということだった。わたしは怪訝(けげん)に思いながらも、病院の玄関の外へ出た。なだらかな坂道を下りながらふと足を止め、くるりときびす踵を返すと再び担当医師の部屋を訪れた。
「先程、どこも悪くないとおっしゃいましたが、わたしはどうもそれが解せないのです」
「ということは?」
「実は」
と鮮血の話をした。
「ああ、腸ですね。腸はこの人間ドックのメニューには入っていません。来週の火曜日にいらっしゃい。わたしの専門ですから一度検査してあげましょう」
あとで人の話によると、谷先生とおっしゃるその先生は、たまたま、腸の権威だったのだ。
人間ドックのときとはお話にならぬくらいの、さまざまな検査の結果、
「ポリープが出来ています。ポリープには良性と悪性とがあって、悪性だとこれは問題です。ともかく早速入院して頂いて、更に詳しく検査しましょう」
ということになった。
この遠回しな説明の中から、敏感な人なら、感ずべきものを既に感じている筈であるが、わたしは、それほど気にも止めずにいた。
検査入院の最中に、付き添って来ていた妻が谷先生に呼ばれ、
「ご本人にはご内密に願いますが、直腸がんです。それもかなり進行しています」
との宣告を受けた。
しばらくは胸の中にしまっていた妻だったが、やがて持ちきれなくなって、大学生の長男にそっと打ち明けた。
「お父さんやったら、言うても大丈夫やろ」
検査入院が終わって許されて帰宅したとき、妻は、わたしに真実を知らせてくれた。しかし、それを聞いたときのわたしは、長男の推測通り意外に冷静だったようだ。
「先生は、どの程度だといっておられる?」
「早期ではないそうです」
「じゃあ、末期か?」
「でもないようです」
「ということは、中期と見てよいわけだ。つまり、どちらへも転ぶ可能性があるということは、元へ戻れるかも知れないということだ!」
わたしは、元へ戻る希望に生きようと、そのとき心に誓った。
ある日、グループのメンバーのお一人で、日頃お親しくして頂いていた平沢興先生に、このことを申し上げたら、先生は即座に、
「医者を信じることです。運命を信じることです」
と、呪文を唱えるようにおっしゃった。
わたしはこの言葉を反芻(はんすう)するうちに、一層、心の落ちついてくるのを感じた。
「そうだ、もしもわたしに、もっと幼稚園の仕事を続けて、子ども達のために尽くしなさい、という神仏のみ心があるとすれば、わたしをこのまま生かして下さるだろう。もうお前の使命は終わったよ。するだけのことをしたのだから、この世に別れを告げていいよ。ということなら、わたしはそれに従えばいいのだ」
全ては神仏の思し召しにある、そう思ったわたしは非常に気が楽になって、平沢先生のおっしゃる「運命に身を任せる」ことにした。
その間、妻の働きでわたしは京大病院で手術を受けることになった。京大病院には、うちの幼稚園へかつてお子さんを二人通わせておられた、第一外科部長の戸部教授がおられる。しかも名医と謳われる先生だ。
妻としては、戸部教授に執刀して頂いて万一駄目だとしても、まだしも諦めはつく。尽くすだけの手は尽くしたいという気持から、わたしの知らぬ間に電話でじきそ直訴したのだった。第一日赤からのカルテをそのまま持って京大病院を訪れたのは、夏休みのさ中のことで、病院の木々の繁みからは蝉の声が降るようにさんざめいていた。
第一外科病棟の病室の空きを待って八月末に入院、九月四日に手術と決定した。
入院前に、急遽、園の先生たちを招集し、二学期からの幼稚園にいろう遺漏のないよう打ち合わせを行い、かつ後事をくれぐれもお願いした。
負けたらあかんで
わたしは手術を受ける前の心構えとして、手術を受けるためには何よりも、
「気力と体力が大切だ。」
そう考えて、毎日三階の病室から屋上まで、一日二回ずつ階段を上がり下りするのを、手術の前日まで続けた。
屋上に上がって東北の方を眺めると、東山三十六峰の左端の方に、小高い瓜生山を臨むことが出来る。この山の頂上に北白川幼稚園がある。わたしは屋上から幼稚園に向かうのを、毎日の唯一の楽しみとしていた。
じいっと見入っていると、やがて子どもたちの喚声が聞こえてくる。羽があるなら飛んで行きたい。子どもたちの喚声は、やがて、
「せんせい、がんばりや。負けたらあかんで」
という激励の声となって聞こえてくる。
「よーし、早う癒って帰るで。待っててや」
わたしも、子ども達の喚声に負けずに、胸の中で大声を張り上げた。
こうして子ども達から勇気と元気を得て、病室へ戻るのだった。子ども達が送ってくれる声援、それに応えて帰りたい、帰らねば!という大きな希望、これが、わたしの入院生活を支えてくれる大きなエネルギーとなったのである。
言いかえれば、わたしは、子ども達の目に見えぬ励ましによって助けられたといっても良かった。
さまざまのご縁
わたしが入院した日、ふと隣を見ると、何となく見覚えのある中年の男性が、二〇度ほど起こしたベッドにもたれて、静かに目をつむ瞑っている。そっと名札を見ると、佐野昭夫とある。
「どこかで見た名前だ!」
やがて目を開けた佐野さんは、
「先生、お待ちしておりました」
「やっぱり」
佐野さんはかつての保護者だったのである。こんなところにも幼稚園との関わりが延長してきている。
彼は二度目の入院で、一度目の手術で人口肛門をつけた。わたしの場合も、どの医師もその必要が一〇〇%あると言われる。
「この頃は技術が非常に進歩していますから、人口肛門といっても私のときとはお話にならぬくらい、便利になっていますよ」
と慰めてくれた。この佐野さんが隣同士になって、先輩としていろいろアドバイスしてくれたり、励ましてくれたりしたことが、手術を受ける気持ちを一層楽なものにしてくれた。
わたしが京大病院へ入院して手術の日を待つ間、妻は家と病院とを毎日行き来していた。手術後は、できれば終始そばにいて看病したいと思っていたが、幼稚園のこと、家のことを考えると、そうもいかなかった。
そうしたある日、病院を出て家へ帰るため、東大路通りのバス停でバスを待っていると、
「牧子先生と違いますの?」
とスクーターを押しながらやってきて、声をかけた人がいる。見ると、かなり前に結婚退職して、今は家庭に入っている綾子先生である。
「何だかしょんぼりしておられるので、別人かと思いました」
綾子先生に出会って、妻もホッとしたのか、思わず溜まっていたものを吐き出すように、事の経緯をるる縷々述べた。聞き終わった綾子先生は、
「わたしがお留守を見させて頂きますから、牧子先生は園長先生のおそばにいてあげて下さい」
思いも掛けぬ申し出に、妻は戸惑った。
「綾子先生こそ、お家があるでしょう?」
「家のことなら大丈夫です。長いことお世話になって、お役に立ちたいのです」
結局綾子先生は、わたしが退院する日まで毎日自宅から通って、園のこと、家のことに心配りを行き届かせ、後顧の憂いなく留守を守って下さった。
長男は、毎日夕暮れになると、先生達からの保育日誌の束を抱えてやってくる。また、こまごまとした報告を聞かせてくれる。同時に、わたしの指示を先生達に伝えてくれる。幼稚園と病院との連絡係だ。大学が病院の傍にあるとはいえ、毎日となると大変だったろうが、そのお陰でわたしは安心して療養に専念することができた。
こうして、多くの園児達といい、戸部教授といい、牧野さんといい、綾子先生といい、家族といい、幼稚園を取り巻くそうした周囲の人達の、不思議なご縁と善意と励ましによって、わたしの入院生活は支えられていた。
脅しと励ましと
さて、話を元へ戻して、手術は、戸部教授の八時間に及ぶ執刀によって、あれほど誰からも不可避とされていた人工肛門をつけずに、無事終了した。
静養のため一週間入っていた薄暗い個室から、元の陽のよくあたる明るい六人部屋へ戻ってきた。枕元には、子どもたちから送られた千羽鶴が、
「手術が、無事に終わってよかったね」
と祝福するように待っていてくれた。あとは、焦らず、じっくりと、徐々に回復を待つばかりとなった。
手術後、悩まされたことの一つに小用のことがある。トイレにいってもなかなか思うように出ない。隣の人は威勢よい音を立ててさっと済ませて行く。わたしは長い時間かかってほんのわずか。
看護婦さんから、
「しっかり出さないと、尿毒症になりますよ」
と脅かされて、気張ろうとすればするほど結果はよろしくない。泣きたい気持ちでいたら、ある日別の看護婦さんが、
「大丈夫ですよ。焦らなくても、今に出るようになりますよ」
と励ましてくれた。
同じ状態に対して、こうも正反対の見解を示されて戸惑いを感じたが、「脅し」と「励まし」と、どちらを取るかと言えば、患者の気持ちとすれば「励まし」の方が有り難いに決まっている。
「よし、焦らないで行こう」
一〇日も経たないうちに正常に戻ってホッとした。
頑張らせようという親切心から出ているには違いないのだが、相手におび脅えを与えるのと、貴方の回復力を信じますよ、と自信を植えつけるのとの大きな違い、これは、母親の、子どもへの言葉の掛け方、叱り方にも共通するものがあるのではなかろうか。
こちらが患者として受け身の立場に立ってみて、しみじみ考えさせられる、看護婦さんの「脅し」と「励まし」であった。
ふるさとへ帰る
かつて、遠く佐賀県から下宿住まいをしながら通勤していた緑先生は、小柄ながら情熱的でピチピチとした先生だった。その緑先生が、学期が終わって故郷へ帰る時の「帰心矢のごとし」そのものの、弾けんばかりの表情が、いまもわたしの脳裏には印象深く残っている。
わたしは一才半の頃、両親に連れられてこの山へ住み着いてから、ほぼ七〇年ほどになる。だからわたしにとっては、ふるさとと言えば、この山がそうなのだろうが、年中住んでいるだけに、緑先生のようなふるさとへ帰る感動は、わたしには永遠に来ないものと思っていた。
病院を出て一ケ月振りに帰る日がきた。忘れもしない九月二六日である。タクシーでバプテスト病院の石の門の傍で降り、第五グループの通園路をそろそろと歩んだ。なだらかな病院下の一本道を折れて、急な山道にさしかかったとき、ふと上の方を見上げて、
「この山道、すごく急やねえ」
傍らの妻を顧みた。
「そうですか。前と変わりませんよ」
と首をひねった。
そりゃそうだ。山道は元の山道だ。しかしそのときの私には、以前の勾配の倍の角度もある急坂に感じられた。一足一足あえ喘ぎ喘ぎ登りながら、入院前なら駆け上がっていたこの道が、全く別の道のように思われた。
長い石段をゆっくり上がる。カラフルな園舎の案内プレート板が目に入る。グローブジャングルのシルバーが太陽に輝いている。
お弁当の時間だろうか、どの部屋からも園児達の喚声は聞こえてこない。でもそのあたり、何となく静かな活気に溢れている。久しぶりの空気だ。ことり組の前を覗きながら通り過ぎ、家の門の前に立つ。
半ば死と背中合わせにあって無事生還したわたしにとって、わずか一ケ月のことではあったが、やはり長い長い旅だった。そして今再びこの門の前に立つ。ほんのちょっとした一木一草にいたるまで懐かしさで一杯だ。
「ふるさとへ帰る喜びというのは、これなんだ。わたしは、今こそ、ふるさとへ帰ってきた!」
黙って、錆びた音のする門扉を押し開いた。
玄関へ出迎えてくれたのは、綾子先生だった。
園長の動けない運動会
わたしは、帰宅早々の一〇月一日のお知らせで、つぎのようなご挨拶をしている。
「おかげ様で去る九月二六日に退院して参りました。
とは申しましても、『すでにこれ以上の外科的処置を施すことは何もありませんので、多数待っておられる入院希望者へ部屋を明け渡して頂くための退院です。
ですからあとは、週一回の外来と、自宅での充分な安静加療を、当分の間は絶対に続けて下さい』との主治医のお話ですので、現場復帰への心ははや逸りますが、いましばらくは目をつぶって、主治医のご指示に従いたいと思います。
いずれ一〇月一三日には保護者会でお目に掛かりまして、ご挨拶申し上げることに致しますので、宜しくお願い申し上げます」
その一〇月一三日の保護者会であるが、一五年前の当時の保護者に最近お出会いしたら、
「今は別人のようにお元気ですね。退院されてすぐの保護者会の時は、すっかりお痩せになって、陰ではみんなで随分心配していたんですよ」
と言われた。
たしかに手術後の体重は、入院前に比べると八キロ減って四六キロにまで落ち込んでいた。無事に帰ってきたとはいえ、頬はこけ、風圧にもよろけそうな、ひょろひょろとした迫力のない姿で皆さんの前に立ったのだから、そう思われたのも無理はない。
正式には一ケ月半程の静養期間を経て園に復帰したのだが、その間に幼稚園にとっては大きなイベントがあった。私の入院騒ぎで、例年よりかなり時期的に遅れて行うことになっている、一〇月二五日の運動会である。
創立当初から若さに任せて、事前の企画や準備、関係方面への手配、当日の進行など一手に引き受けてきたパターンが、前年度まで継続されていただけに、まず先生たちが、園長なしでどうやって行くのだと、ハタと困った。何もかも、自分達で一から組み立てなければならない。
それとその年は、例年、運動会場としてお借りしている北白川小学校の運動場が、整備のために使えなくなった。やむを得ず、宝ケ池の児童遊園地へ場を移すこととなったが、この場所でやることには、全く慣れていない。運動会用具も、小学校から借用物を運んでくるか、あとはすべてレンタル店からの借り物で賄(まか)なうことになる。
先生たちは、前年度まで残してきた私の資料と首っ引きで準備を進めるのだが、会場が違うということが、これほど大きなあいろ隘路になろうとは思いも寄らなかった。すべてが困難な状況の中で行われたにもかかわらず、大過なくやり遂げて貰ったのだから、その年の先生方には本当にご苦労をかけたと、今も感謝している。
と同時に、動きの取れない私を見かねて、大学生だった長男が、今までの見よう見まねでレンタル店との交渉から、当日の進行等々、運動会運営の一翼を担ってくれたこと、また、同じく大学生だった次男も、平日のために僅かだったお父さん方のお手伝いに混じって、準備係や演技の補助に飛び回っていたことなど、わたしには、思いがけなく嬉しい出来事であった。
そのようなことで、保護者会と、運動会の日にだけは何とか顔を出したが、退院後ほぼ一ケ月半ほど、ふだんはまだ家にいて専ら静養に努めなければならなかった。
戸部教授のお陰で人工肛門こそ付けていないが、何しろ肛門近くの手術なので、術後はじっと坐ることさえ容易でない。まともに坐ろうとすると、激痛が突っ走る。だから、病院でもそうだったが帰宅後しばらくは、中央部に穴のあいたドーナツ型の丸いクッションの上で、腫れ物に触るように、肛門をそろっと宙に浮かせながら坐って、辛うじて痛さを凌いだ。
運動会の本部席に坐っていたときも、実は、顔で笑って後ろで泣いていたのである。
子どもが恋人
そんなわけで、とくに病院から帰宅直後のしばらくは、午後の昼寝と、何もかも忘れてリラックスすることに専念した。
当然のことながら、幼稚園へ一日も早く出たい気持は山々だ。だが、かつての失聴状態の時、関節から関節への痛みの時、ともに一ケ月の休養を貰って次ぎに備えたことがある。今回も一ケ月間余、あえて幼稚園へは顔を出さず、はや逸るこころを抑えて力を溜めることにした。
とはいえ、一方において幼稚園へ復帰するための準備を、怠っていたわけではない。
できるなら、まだ人に顔を合わせたくないので、日が落ちて暗くなってから、少しずつ少しずつ足ならしのための散歩を、かなり早くから始めていた。
初めは山の下までの往復、山の下からバプテスト病院を経て山を一回り、上終児童公園、一乗寺のバッティングセンター、木ノ本町バス停、と次第に足を延ばして、最終段階では、修学院道近くの「ブルグ」でパンを買って帰る、というコースが恒例の道となった。
一と月半ほど経って、ふたたび送り迎えの先頭に立った。わたしも子どもたちも久しぶりに合わせる顔である。お互い何となく照れた感じで、子ども達もその日はことのほか粛々とお利口に歩いてくれた。私の病後への労りの気持もあったのかも知れない。
こうして私は次第に平常の園生活へ戻り始めていた。
よわい五六才の年に手術をして、今年(九九年) の九月で丸一五年。七〇を越えた齢となった。
たしかに白髪は増し、耳は遠くなり、視力は落ちて、機能的にはいささかの衰えを覚える。これは誰しも辿る自然の道筋である。
しかし、当時と比べて、気力だけは衰えていないつもりだ。むしろ手術前より高揚しているかも知れない。それにまだわたしには、何よりも、今もなお確かな足がある。
子ども達を迎えに行くために、わたしは毎朝七時五〇分には家を出る。七時半を過ぎると、わくわくしてくる。そわそわしてくる。妻が、
「まるで、デートに出かけるみたいですね」
と笑う。
「そうなんや。子どもが恋人なんや」
と私も笑う。
最近、ある卒園児の保護者から、
「一〇年前とちっともお変わりになりませんね」
といわれたことがある。多分にお世辞も混じっているとは思うが、たしかに気分だけは、三〇代は厚かましいとしても、四〇代、五〇代の頃と変わっていないつもりだ。少なくとも子ども達に向かうとき、七〇代の老人の意識は全くない。
信号を渡るときには子ども達とともに駆けて渡る。時には、列の後方の子どもたちへ大声で呼びかけながら、後ろ向きに大股で駆けて渡る。人がその姿を見て怪訝(けげん)な顔をする。
こうした元気の源は、大きな手術で病気を一切病み捨てたこと、幸い、わたしの身体に合った漢方の薬に恵まれて、手術後今日にいたるまで一日も欠かさず飲み続けているお陰もある。しかし、何よりの根源は、子ども達から享受するエネルギーの迫力にあると思う。
子ども達は全身一杯で話しかけてくる。それを受けるのに、老人っぽくぼそぼそと受け答えしていたのでは、つぎから子ども達は話しかけてくれない。全身一杯に対しては全身一杯である。それが手術前後にはできなかった。気力が伴わなかった。よほど疲れていたのであろう。
だから今は毎日が楽しくて仕方がない。体当たりでぶっつかってくる子どもがいる。両手を持ってぐるぐる廻しを要求してくる子どもがいる。子どもたちは老人への労りを示してくれない。有り難いことだ。まだまだこれからも子ども達と関わってよいという、これは子ども達からのメッセージなのだ。
わたしは、心の中で決めていることがある。
「もしも保護者の目遣いの中に、わたしの送り迎えの足取りから少しでも不安を感じるものが、チラとでもうかが窺えたら、わたしは即刻、送り迎えから足を洗おう。」
しかし今のところ、保護者の私を見る目にその気配は感じられない(ように思う)。
せっかく病み捨てたのだから、これからも子ども達から精一杯のエネルギーをいただき、わたしも子ども達に精一杯の真心でお返ししながら、生き甲斐のある余生を送りたいものと思っている。