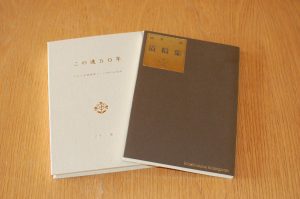幼児期に遊ぶことの意味
「お宅の幼稚園では、主に、どんなことを教えておられますか?」
毎年、入園申し込みシ-ズンになると、こんな質問を多く受けます。それに対して、
-わたしどもの園では、特に何を教えるということは致しておりません。
-何よりも、遊びを大切にしております。幼児期でなければ得られないいろんなことを遊びを通して学んで頂いております。
-それとともに、この山の上でうんと遊び込んで頂いて、心とからだを強くしながら、幼稚園時代の楽しい思い出をいっぱい作って行って頂くことを、何よりの願いとしております。
このようにお答えしますと、わが意を得たりという顔をなさるお母さんもいらっしゃれば、何となくがっかりとした表情を浮かべられるお母さんもいらっしゃいます。お考えは人さまざまですからこれでいいのですが、早期知的教育を受けさせたいと思われるお母さんには、どうやら物足りなく思われるようです。
たしかに「遊ぶ」といえば、お母さん方には、 「遊んでばかりいて、少しは勉強したらどうなの!」「あの幼稚園は、遊ばせてばっかりいて!」といったふうに、あまり芳しくないイメ-ジで捉えられがちですが、幼児期における遊ぶという行動は、大人の世界でイメ-ジする遊びとはぜんぜん違っておりまして、幼児の発達の上からも、将来への人間作りの基礎という点からも、じつは、たいへん重要な意味を持っております。
遊びがなぜ勉強なのか
では、遊ぶことがなぜそんなに重要なのか、遊びを通して子どもはいったい何を勉強しているのか、そうしたことについて触れてみたいと思います。
例えば、5人の子どもが集まったとします。5人いれば、そこには5つの心が息づいています。5通りの考えがあります。感情もみな違います。家庭環境による育ち方もみな違います。その5人の子どもたちが、あるとき、何かして遊ぼうということになります。そこは、家庭にいるような親の保護や干渉のない、子どもたちだけで展開していく、まったく自由な世界です。ときには、中にリ-ダ-的な子どもがいて、その子の発案にあとの子どもたちが従うという場合もあります。
しかし、そうした子どもが特にいない場合、子どもたちはみんなで相談します。先ず、相談のためにはおたがいに自分も希望を言い、人の希望も聞かねばなりません。自分が言うということは、自分の意見を持ち、その「自分の意見」を、人前で「発表」するということです。
一方、人の希望を聞くためには、人の意見を「理解」しなければなりません。そのためには、人の話を「よく聞く」という姿勢が必要です。みなの希望が出揃ったところで、こんどは、それらの希望を集約し、みんなでどれか一つの遊びに「まとめ」ねばなりません。まとめるためには、ひとりひとりの「協調」の気持ちが大切です。必要とあらば、新たにル-ルを「作る」場面も出てきます。そこで5人の子どもたちは、ふたたび頭を寄せ合います。
こうして、遊びを始める前の段階においても、すでに5人の子どもたちは、「自分の意見を持つ」「それを発表する」「よく聞いて」「理解する」「まとめる」「協調する」「作りだす」といった、いくつかの工程を、くるくると頭を働かせながら、短時間の間の処理をやってのけています。なおその上に、子ども同志の刺激やぶっつかり合いを通して、言葉の分量が増え、「語彙が豊富になる」ということがあります。
生きた智恵としての遊び
こうして見ますと、子どもたちが相談し合ったこれらの経緯の中には、いってみれば、小学校へ行ってからの「国語」の勉強において要求されるものが、つぎつぎに登場しています。
また、大人になってからの社会性は、子ども社会において養われたものが、基盤となっているのですから、5人の子どもが協調しながらまとめ上げて行く経過は、まさしく、生きた「社会」の勉強そのものです。
子どもたちは夢中になって遊びながら、走る,跳ぶ,転がる,投げる。知らず知らずの内に、身体中の筋肉を、骨格を、神経をフルに動かしているうちに、「体育」の勉強をしています。
遊びながら、跳ね回りながら、会話を交わし合いながら、時にはけんかをしながら、時には譲り合いながら、子どもたちは遊びを通じて、生きた「国語」や、「社会」や、「理科」や「体育」や、さまざまの学習,勉強をしているのであります。
単純に、無機質なドリルの紙上で、人との会話もなく、けんかもなく、ただ一つだけの正解を求める“ひとり静かな勉強”とはまったく違います。その場その場の顔ぶれや状況に合わせて、多様な解答の中から一つの正解に導いていく知恵、これこそ、「生きた知恵」であり、「生きた学習」です。
しかも、幼児にとって遊びは楽しいのです。けんかしても、また明日遊びたくなる、これが幼児の常です。この、幼児期の楽しい遊びを通して得た生きた知恵が、小学校へ行ってから役に立つのです。この知恵が、国語や算数や、そのほかいろんな勉強の場面において、単にマニュアル通りの知識をたくさん知った、覚えたというだけでない、応用の効いた、その子ども独自のオリジナルな解答を生みだしてくれるのです。
幼児期に芽生えたオリジナルなものの見方,考え方の芽が、やがて世の中へ出てから枝葉を伸びやかに拡げ、独創的な仕事を生み出す大きな原動力となってくれます。
これからの、21世紀の日本の社会において求められるものは、この物真似でないオリジナル性であります。遊びを通して得る個々のオリジナル性を、これからの日本の将来のため、幼児期から、もっともっと大事に育てるべきではないでしょうか。
わたしどもの園で、遊びを大切にしている意味は、そこにあるのです。