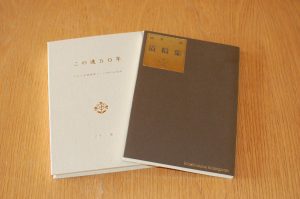「ヒト」は歩くことによって「人」となる
“「ヒト」は歩くことによって「人」となる”といわれています。その考え方からしますと、歩くことを忘れた現代人は、これから先、だんだん「人」から遠のいていくように思われてなりません。いま、高齢化の問題が取り沙汰されていますが、いまのまま進んでいけば、遠からず、高齢化問題もさほど心配しなくてすむ時代がくるのではないだろうか?
そんな予感さえするのです。 いまの幼児たちや、30代,40代の保護者の皆さんに日常接していますと、この人達の中で平均年齢80何才という高年齢まで生き残れる人が、果してどれだけいるだろうか、不謹慎ですが、ふと、そんなことを思ってしまうのです。
むかしの遠足
明治,大正,それに昭和初期の、現在高齢者もしくは高齢に近い人たちは、歩くということひとつ取って見ましても、幼少期からたいへんな歩行量を蓄積してきており、それが今日の高齢化を支える健康の土台となっています。わたしが小学校へ通っておりました昭和10年代の頃を思い起こしてみましても、遠足といえば、春と秋に適応遠足というのがありました。その名の通り、学年に適応した目的地が選ばれるのですが、とくに6年生ともなりますと、春はわたしたちの小学校のある北白川から、平安神宮,清水寺を経由して、伏見桃山の近くの御香宮まで。
秋は八瀬から三千院を経て大原の寂光院まで、どちらも往復ほぼ16キロの道のりを歩くというのが恒例になっていました。それは大変な強行軍でして、小学校へたどり着いたときには、さすがにみな疲労困憊、声も出ないほどでした。
今日のバス遠足のことしかご存じない人たちから見れば、当時の遠足はそれこそ鍛えに通じる厳しさと写るかも知れません。しかし、6年生として小学校生活最後のイベントを落伍することなくやり通した充実感は、今思い起こして見ましても爽やかな感動となって蘇ってきます。わたしたちの昭和初期でさえ、こうなのです。明治,大正の時代の方たちは、日常生活のすべてがごく自然のうちに鍛えに通じていて、今のしっかりとした足腰のもとを作ってこられたものと思われます。
クルマ社会と子どもたち
そこへいきますと現代は、歩いて10分とかからぬところへ行くのにもクルマ。公共施設には、ほとんどのところでエスカレ-タ-やエレベ-タ-が設置されています。場所によっては動く歩道まで用意されています。すべて便利で、文化的で────。これではまるで、人に、歩くな、歩くな!弱くなれ、弱くなれ!と奨励しているようなものです。こうした時代的背景の中で、今の幼児たちは育つのです。歩く場を奪われ、歩くチャンスを奪われ、歩く時間を奪われている子どもたち。「健康は足から」といいます。「高齢化は足から」といってもいいでしょう。
歩いての送り迎え
そこで、幼児教育に携わる者として、せめて幼児期においてだけでも、しっかりと歩いてほしい、うんと歩き込んでもらいたい。そして、将来をめざした体力の基礎づくりに役立ててほしい。
切実にそう願って、わたしどもの幼稚園では先生と園児とが一体になっての“歩いての送り迎え”を、創立以来ほぼ50年近くにわたって実施してきております。
もっとも、当園が“歩いての送り迎え”を始めました最初の頃は、子どもと先生,子ども同志,相互の心の交流を図る場としての登降園でありまして、いまのように、“歩くことの意義”を真剣に考えるようになりましたのは、クルマ社会が急速に発達してき始めました30年くらい前からのことであります。
では、わたしどもの幼稚園で、この歩いての送り迎えを実際どのように日々実施しているのか、子どもたちのそれに対する反応と効果はどうなのかについて、具体的にご紹介してみたいと思います。
唯一頼みとするは、自分の2本の足のみ
わたしどもの北白川幼稚園は、京都市内の北白川という比較的閑静な場所にあります。しかも、東山三十六峰の峰々の一つにあたる、北白川山という小高い山の頂上に建っています。ですから、別名「お山の幼稚園」という呼び名もついております。
高さは海抜100メ-トルということですが、麓のあたりがすでに海抜70メ-トルだそうですので、麓から山の上までの実際上の高さは、おおよそ30メ-トルということになります。30メ-トルの高さということは、8階建てのデパ-トの屋上とほぼ同じといっていいでしょう。
デパ-トの屋上へ上がるには、だれしもエレベ-タ-かエスカレ-タ-を利用します。いまどき、横手の階段を一階から屋上まで黙々と歩いて上がる物好きな人は、ほとんどいません。屋上と同じ高さの山の頂上へ、石の階段の延々と続く山道を、日々幼児が歩いて登るのです。もちろんクルマは麓からは上がってこれません。上がるのに、唯一頼みとするは、自分の2本の足のみです。
「たいへんな所に幼稚園がありますね」
初めていらした方は、たいてい、「たいへんな所に幼稚園がありますね」 と目を丸くされます。それだけではありません。「じつは、この麓へくるまでに、園児たちは先生に連れられて、遠いところは1キロ近くの道を歩いてくるんですよ。」と申しますと、どなたも二度びっくりされます。
グル-プは5つありますので、多少出発地点からの歩行距離に長短はありますが、近いグル-プでも200メ-トルや300メ-トルという短い距離ではありません。そうした長い道を、2人,3人手をつなぎながら、長い列を作って歩きます。グル-プの人数にもよりますが、だいたい前と後ろに先生がつきます。わたしも一つのグル-プの前を受け持っています。わたしは、長い列の先頭に立って後ろ向きに歩きます。こうしますと、第一に長い列のうしろまで見通せます。
それに何よりも、子どもたちと向かい合って、子どもたちの顔を見て、子どもたちとおしゃべりをしながら歩くことができるからです。
「後ろ向きで上手に歩かれますね」
これはわたしどもの園の創立以来のわたしの送り迎えスタイルでして、見知らぬ通りがかりの人からも、「後ろ向きで上手に歩かれますね」と、声をかけられることがあります。
よく冗談で、「わたしは終生後ろ向きの人生で、だからちっとも進歩がありません」と笑うのですが、50年近くもつづけてきますと、慣れでしょうか、頭の後ろに眼ができてくるものとみえ、幸い事故らしい事故にあったことはありません。
「せんせい、うしろにお馬さんのうんこが落ちてるよ」 と、かつて一乗寺の野道を歩いていた頃は、そんなふうに教えてくれてきた同じ道が、いまでは完全に舗装されて家も立ち並び、「せんせい、けさはお家からクルマのお尻がでてるよ、気いつけてね」と注意してくれるようになったのも、時代の移り変わりのせいでしょうか。
このようにして、毎日送り迎えの行き帰り2キロ近くの道を後ろ向きになって、ハンメルンの笛吹きおじさんよろしく、子どもたちを連れて歩いております。
「ぼくが守ってあげなければ」
さて、その子どもたちですが、見ていますと、3才児を中にして、近所の4才児,5才児のお兄ちゃん,お姉ちゃんが手をつないでくれることもあります。3才児同志で大きい人たちに遅れないようがんばって歩いている姿も見かけます。たしかに、入園してしばらくは、送りの途上くたびれの出る3才児も見かけます。
4月末の、お弁当持ちのある日の帰り道のことでした。あいているのか、つむっているのか、もうろうとした目を宙へ泳がせながら、ふらりふらりと歩いている一人の3才児が列の中にいるのを発見しました。わたしはさっそく、列をとめてその場へ走っていこうとしましたが、よく見ますと、その3才児の左右にいた2人の5才児が、時折よろけそうになる3才児を、両側からしっかりと支えながら歩いています。
2人はだれに頼まれたわけでもないのに、また、2人で相談し合ったわけでもないのに2人の呼吸はぴったりと合って、じつに見事にガ-ドしてくれています。その1人1人が、
「ぼくが守ってあげなければ」
といった気持ちなのか、真剣な表情で3才児を介助している光景を見て、深く感動させられたことがあります。もちろんそうした3才児には、保護者と連絡を取りまして、当分の間、その子の疲労の程度に合わせて山の下の麓近くまでお迎えをお願いしますが、5月半ばともなればどの3才児もみんなと同一歩調がとれるようになってきます。
歩くことの楽しさ
ところで、遠い距離を歩かせるということは、子どもたちにあるいは大変な困難を強いているように思われるかも知れませんが、慣れれば子どもたちは、家を出て公園で集まって幼稚園に着くという行程を、家のなかの部屋から部屋へ移るのと大して変わらない気分でこなしています。
どうしてそんなに遠い距離を、子どもたちは負担にも思わず行き来しているのかと申しますと、もちろん慣れもありますが、結局は“行き帰りの道が楽しい”の一語につきるようです。ですから有難いことに、慣れてしまえば、歩くのを嫌がる子どもはひとりもいません。
歩くのが嫌で幼稚園をお休みしたという子どもは、まだ聞いたことがありません。雨降りの朝でも平気です。では、その楽しさとは何なのかと申しますと、まず第一に、歩きながらの先生やお友達との弾んだ会話です。わいわい、がやがや、にぎやかにお喋りをしているうちに、知らぬ間に幼稚園についていた、という感じです。
もちろん、20年前、30年前とは交通事情も違っています。その方にも気を配らねばなりませんし、子どもたちの話にも応答してやらねばなりませんので、引率する先生たちは、山の麓まで無事到着すると、ホッとすることは事実です。
歩く場はしつけの場
月曜日の朝など、前の方にいる子どもたちから日曜日の出来事を先生に聞いてもらいたくて、われ先にと口を開いてきます。そこで交通整理をしなくてはなりません。
「Aちゃんがいちばん先に言いだしたから、みんなでAちゃんのお話をまず聞いて上げようね。つぎはBちゃん。」順番を守って、人の話をよく聞く、というル-ルを最初に作っておきますと、なんの混乱も起きません。話す人も安心して話せます。また、待っていれば自分の話もみんなに聞いてもらえます。子どもたちの歩く歩道上は、ル-ルを守ることが安心感を生み、たのしさにもつながるんだということを身につけていく、しつけの場でもあるのです。
ある朝の子どもたちの会話の録音です。 「きのうねえ、Cちゃんのお誕生日だったの。それで、わたし行ったのよ。そうしたらね、Cちゃんのお家の前で、Dちゃんがしょんぼりしてるの。どうしたの?って聞いたら、朝からお母さんがお出かけしてて、プレゼント持ってこれなかったんだって。それでね、わたしの持ってたプレゼント、“これ、ふたりからって言って渡そうよ”そう言ったの。そうしたらDちゃん、“ありがとう”言って、とってもよろこんでいたわ」これは、いつもお友達に優しいEちゃんの話です。
「ぼくの弟のFがね、きのう口を開けたらね、歯茎のとこが白くなってるの。あれねえ、歯が生えてくるしるしなんだって」Gちゃんは、赤ちゃんの弟が大好きで、いつも口を開くと赤ちゃんの成長ぶりを手に取るように報告してくれます。
歩く道は、生きた保育室
子どもたちが毎日楽しみにしているのは、会話ばかりではありません。歩きながら周囲の四季の環境の移り変わりや、生き物の日々の動きに目を向けることもまた、子どもたちの楽しみの一つなのです。小料理屋さんの軒先の巣に、ツバメが帰ってきたのをいち早く見つけたのも子どもですし、大通りから少し離れたマンションの7階に、ある朝、小さな団地鯉のぼりが上がったのを教えてくれたのも、子どもです。
「ほら、あのピンクのあじさい、昨日より色が濃くなってるわ」花の色の変化にも敏感な女の子。通りがかりの一軒の家に繋がれている犬の様子を見て、「きょうは、なんだか元気ないな。暑いからかなあ。吠えないで、じっとこっち見てるだけだよ。元気だすんだよ」と心配したり、励ましたり。
「あっ、いつも走り廻ってる子猫が、きょうはお母さん猫のお腹の下にくっついてる。きっと寒いから、お母さん温めてやってるんだね」ホッとする子どもたち。
ある朝、歩道の端で一匹の猫が横になっていました。遠くからは寝ているように見えていました。傍を通りかかったとき、一人の男の子が、「この猫、寝てるのとちがうね。死んでるよ」 「ほんとだ、血がいっぱい出てる。車にひかれて、はねとばされたんじゃないかな?」
それからしばらくは、ひかれた猫の話題で持ちきりでした。かわいそうだという声の多いのは勿論ですが、「やっぱり、信号の通るところを渡らないから、だめなんだね」
「ねこに信号、わからないよ」
「だれかが教えてあげたらいいんだよ」
「でもねこは人間の言葉がわからないんだよ」
「それでも、猫にだって“いのち”はあるんだよ」
子どもたちにとって、行き帰りの歩く道は、自然の美しさを、目で確かめ、耳を澄まし、においを嗅ぎ、心で問いかける場でもあり、また、生き物の育ちやいのちに心を通わせる、優しい心情をはぐくむ場でもあるのです。毎日同じ道をくり返しくり返し歩きながら、健康の基礎である脚力が、いつのまにかしっかりと身についてくるのは当然ですが、先程来申してきておりますように、日々歩くこの道は、
楽しい会話の場であり、
友情を温める場であり、
自然観察の場であり、
社会勉強の場であり、
感性を育てる場であり、
優しい心情を育む場であり、
交通ル-ルを身につける場である
ということです。
言いかえればすべてこの道は、生きた保育室、動く保育室に通ずるといえるのであります。
歩く道は、心を強くする場
行き帰りの歩く道は、子どもたちにとって楽しい動く保育室であると同時に、さらに大切なことは、この道が心を強くする場でもあるということであります。
ある年の、忘れもしません4月18日のことでした。4月18日といえば、新入園児にとっては入園後1週間たつかたたぬかの、まだ園生活にもほとんど慣れていない不安でいっぱいの頃です。
その朝、子どもたちが親に連れられて集合場所の児童公園に集まって来た8時過ぎは、4月には珍しく、黒雲が異様に低く垂れ込めていて、まるで、夏の夕立前を思わせる空模様でした。23人の3才児を含む60人ほどの子どもたちの長い列を引率して、児童公園を出発してから10分ほどたった頃です。
白川通りに面した芸術短期大学の前あたりまでさしかかると、あたりが急にいっそう暗くなって、それはほとんど瞬時のことでしたが、稲妻と雷鳴とが交錯したかと思うと、激しい驟雨が、子どもたちの列の上にまるで襲いかかるかのように、いっときに降り注いできました。
さいわい、朝から不穏な天気であったために、子どもたちは一様に雨具の用意はしてきていました。そこで、二人の先生といっしょになって、手早く開けない子どもの傘を開いてやり、レインコ-トを着せてやり、慌ただしく動き回っておりましたが、その間、子どもたちは不安の極限に立たされたためか、泣くことさえ忘れて、正に茫然自失の体でありました。
いずれにしましても、ついこの間までならすべての行動をほとんどお母さんとともにしていた3才児ばかりです。当然のことながら、この様な場面に遭遇したら一も二もなくお母さんにしがみついて泣き叫ぶところでしょう。だいいち、その朝のにわか雨は、大人のお母さんだって心細く思われるような、まさに晴天の霹靂、車軸を流す雨はしぶきとなって、下から激しく、容赦なく叩き上げてきます。昨年から来ている4才児,5才児だって、顔が極度に硬直しています。
この際、3才児の誰かひとりが、茫然自失の状態からふと目覚めて激しく泣きだしたら、それこそ連鎖反応で、どうにもこうにも収拾がつかなくなってしまうでしょう。といって、いまさら児童公園へ引き返すわけにもまいりません。お母さん方はすでに家路について誰もおられません。ぜったいに後戻りはできません。
とにもかくにも幼稚園へ向かうよりほかありません。 「泣かないでくれ!泣かないでくれ!」 祈るような気持ちで、一歩一歩、薄氷を踏む思いで、歩を進めて行ったのでした。
そしてその結果、どうだったかと申しますと、ついに誰れひとり泣く子どもはなく、山の上までぶじに到着することができました。にわか雨のことで、途中から雨足もゆるやかになり、どす黒かった空の色にも何となく明るさが見えてきました。
そこでホッと気がゆるんで泣きだす子どもが出てこないかと、わたし達はまた別の新たな心配を持ち始めていましたが、子どもたちは初めての怖かった体験を反芻するかのように、どの子もひたすら黙々と歩きつづけてくれたのです。
傘をさすことに慣れなくてびしょ濡れの3才児もかなりいました。先生たちは部屋へつくなり、それらの子どもの上着から下着からの総取り替えのため、その日は、予定のカりキュラムの半分も消化することができませんでした。
しかし、カリキュラムの完全消化にも増して子どもたちは、生きた体験、生きた大仕事をやってきたのです。ママのそばでは知ることのできない強い心が自分のなかにあることを知り、それを育てることができたのです。そしてやり通したことの喜びを掴み取ることもできたのです。
この日は、子どもたちにとっても、先生たちにとっても、充足感でいっぱいに満たされた、生涯忘れ得ぬ一日となったのではないでしょうか。毎年子どもたちは、この日のような驟雨ばかりでなく、凍てつく冬の朝、強い陽射しの照りつける夏の午後、そのほか天候上の悪条件に出会うことはしばしばです。
しかしそのつど、親や、祖父母など、大人の前では見せない、3才児は3才児なりの自立心をもって、耐え忍び、さいごまでやり通す、強い力を発揮して、毎日元気に通ってきてくれます。
この道は、子どもたちのそんな強いこころを引き出してくれる道でもあるのです。
Mちゃん、正月の都大路を歩く
毎日歩きつづけていますと、どの子にも、歩くことに何か自信めいたものがついてくるのでしょうか、「今度の日曜日、大文字山、みんなで登ろうな」 と率先して家族に呼びかけるなど、新たな目標に向かって挑戦の心をかき立てるようであります。いうなれば、子どもたちにとっては、日頃の徒歩通園の応用編といったところでしょうか。
いちど、こんなことがありました。5才児のNちゃんは、冬休みに家族揃って白浜へ一泊し、その日の午後5時過ぎに京都駅へ帰ってきました。さっそくタクシ-乗り場で車を待ったのですが、お正月早々のことで、なかなか順番が回ってきません。長蛇の列で3,40分は待たねばならないかも知れません。家族が少しいらいらし始めた頃、Nちゃんが突然、「ぼく、歩く」 と言いだしたのです。
「歩くって、家までか?」
「そうだよ。ぼく、歩くの平気だよ。足、丈夫だもの、自信ある」
これには両親も、えらいことを言いだしてくれたものと、思わず顔を見合わせましたが、Nちゃんの、幼児とは思えぬ毅然とした顔つきに、
「よし、歩こう!」
さいごは、お父さんの鶴のひと声で、みんなはテクテクと烏丸通りを北上し始めました。たしかに、京都駅からNちゃん一家の住む高野の公団住宅までは、遠い道のりです。少なくとも8キロはありましょう。
(この遠さが、この子には果して分かっているのだろうか?)
お父さんは、先ずそのことを思いました。だからお父さんにしてみれば、初めのうちは、
(途中でへこたれたら、そこからクルマを拾えばいい)
それくらいの気安さだったのです。
一行が、烏丸通りを東へ折れて、鴨川沿いの川端通りを歩く頃にはあたりはすでにとっぷりと暮れて、人けのない正月の宵闇の中を黙々と歩く一行の靴音だけが、凍てた道にひびきました。
賀茂大橋を越えた頃、小学校2年生のお姉ちゃんが、
「もう、歩けない」と訴えました。
「N、どうだ?」
「ぼく、だいじょうぶ!」
ポツリと、しかし、力強い声が帰ってきました。そのころになると、お父さんの胸の中には、この子の初志を貫徹させてやろうとの思いが、ふつふつとたぎっていました。 (さいごは、おぶってやっても、クルマにだけは乗るまい) やがて、街頭の薄明かりの向こうに、わが家の門灯を見いだしたとき、Nちゃんは思わず「やったあ!」 と、歓声をあげました。
「すばらしい正月だったなあ」
お母さんを省みて、お父さんは感慨深げにつぶやきました。
何日かたってお父さんが、
「あの日は、つらかったろう?」と聞きますと、
「そりゃ、つらかったよ。でも、ぼく歩くっていったら、さいごまで歩いただろ」 と、胸を張ったということです。
かれが成長して、何かの困難にぶっつかったとき、
“ぼくは5才のとき、都大路を足をひきずりながら、言った言葉にさいごまで責任を持った。今ここでくじけては、幼い日の自分に恥ずかしい!”
そこで、かれの強靱な意志は、見事に蘇ってくれるのではないでしょうか。
ヒトが「人」として育つために
物質に恵まれ、文明の恩恵に浴し、便利さに慣らされている現代だからこそ、ヒトが「人」として育つためにも、歩くことを通して、
不便と立ち向かい、
我慢すること、
耐えること、
忍ぶこと、
そしてそれらを克服したときの、
真の強さ、
真のたくましさ、
真の喜びを自覚させてやりたい、
そういう思いに駆られながら、今日も子どもたちの前に立って私は後ろを向いて歩みつづけております。