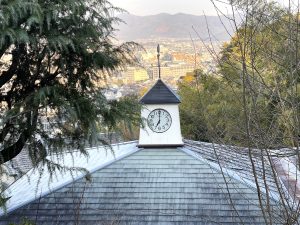連休中本棚を整理していると、祖父(1914-1968)の書いた本が目に留まり、しばらく読みふけりました。タイトルは『福祉の思想』(糸賀一雄)。祖父は54歳で他界するまで、持病の心臓病を抱えながら、よくお山の幼稚園の石段を登って初孫である私に会いに来てくれました。父と教育の話を交わしていた姿を今も思い出します。祖父は滋賀の南郷に「近江学園」を設立し、知的障害のある子どもたちの福祉と教育に一生を捧げました。
著書の中に「この子らを世の光に」という言葉があります。本園の教育に深くかかわる言葉ですので、文脈をご紹介しましょう。
「この子らはどんな重い障害をもっていても、だれと取り替えることもできない個性的な自己実現をしているものである。人間と生まれて、その人なりに人間となっていくのである。その自己実現こそが創造であり、生産である。私たちの願いは、重症な障害をもったこの子たちも立派な生産者であるということを、認め合える社会をつくろうということである。『この子らに世の光を』あててやろうという哀れみの政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよ磨きをかけて輝かそうというのである。『この子らを世の光に』である。この子らが、生まれながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障せねばならぬということなのである」。
私はこの文を読み、「この子らを・・・」は、すべての子どもたちの教育に示唆を与える言葉だと思いました。障害の有無にかかわらず、子どもたち一人一人の可能性を信じ、努力の一歩一歩を応援し、励ますことは本園のモットーであり、日々の実践そのものです。徒歩通園の意義を信じて本園を選んでくださった皆様にはご理解いただけると思います。「まだ小さいから」という理由で自分の足で歩けるのに歩かせない、「可愛い子だから」という理由で旅をさせない。これも愛情の現れに違いありません。しかし、「可愛い子だから旅をさせる」という価値観は、どれだけ時代が進んでも古びるものではありません。
「この子らを世の光に」という言葉について、ある人は次のように説明しています。
「障害児は「愛され、保護されるべき『客体』」として考えられがちでした。いうなれば「この子らに世の光を」というのが、当時の、ともすれば今でも、障害児に対する福祉の姿勢です。しかし、糸賀は、障害を持った子どもたちの生活の中に「より自分らしくあろう」「よりよく生きよう」という自己実現の意欲を見ました。それは、健常者と変わらないどころか、健常者よりもひたむきな、それぞれの個々のかたちでの「生」への歩みであり、「創造」「生産」であると糸賀は感じました。そこで糸賀は「を」と「に」をひっくり返し、「この子らを世の光に」という言葉を使って、それまでの主体と客体を逆転したのです。つまり、障害を持った子どもたちこそが、光を放ち社会にアクセスして輝かせる「主体」となるべきなのであり、「客体」ではないこと、主体であらねばならないことを、糸賀はこの言葉で表現したのです」。
この表現のうち、「障害児」を「子どもたち」、「健常者」を「大人」と読み替えれば、本園の教育の姿勢と一致することに気づくでしょう。子どもたちをか弱い存在と哀れみ、彼ら<に>慈悲をかけるのではなく、一人一人の「よりよく生きよう」と努力し挑戦する姿に敬意を払いつつ、子どもたち<が>世の一隅を照らす輝ける存在に成長するよう心から願い、応援する、というのが私たちの目指す教育である、ということです。
もう一つ、祖父の言葉を紹介します。
「脳性小児麻痺で寝たきりの一五歳の男の子が、日に何回もおしめをとりかえてもらう。おしめ交換のときに、その子が全力をふりしぼって、腰を少しでも浮かそうとしている努力が、保母の手につたわった。保母はハッとして、瞬間、改めて自分の仕事の重大さに気づかされたという」。(『福祉の思想』より)
一学期の始業式に先立ち、私は本園教職員にこの言葉を紹介しました。脳性小児麻痺の子はこういうもの、自分では何もできない、と決めつけてしまっては、この「ハッとする」瞬間を逃したでしょう。引用文にある輝く「瞬間」は子どもたちと過ごす日々の保育の中に無限に見出せる、それを見逃さないように努めよう、と私は呼びかけました。
日本語に「出る杭は打たれる」という言葉があります。見方によっては、小学校入学時にはどの子も「出る杭」だらけです。我が国の教育は、この凸凹を「自ら輝く素材そのもの」と認め、互いが互いを尊重し「認め合える社会をつくろう」としているのか、それとも、一人一人の凸凹を削って均等に調え、無難な「人材」に仕上げることを目指すのか(すなわち、挑戦を遠ざけ、失敗を回避させることを第一に考えるのか)。今一度反省する時が来ていると思います。私は子どもたちの「生まれながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障」すべき点で、教育も福祉も理念の差はないものと考えます。
このように考えたとき、「この子らを世の光に」という祖父の残した言葉は、本園の目指す教育の前途を照らす言葉のように思われ、あらためて勇気を得た次第です。
令和4年5月26日 園長だより